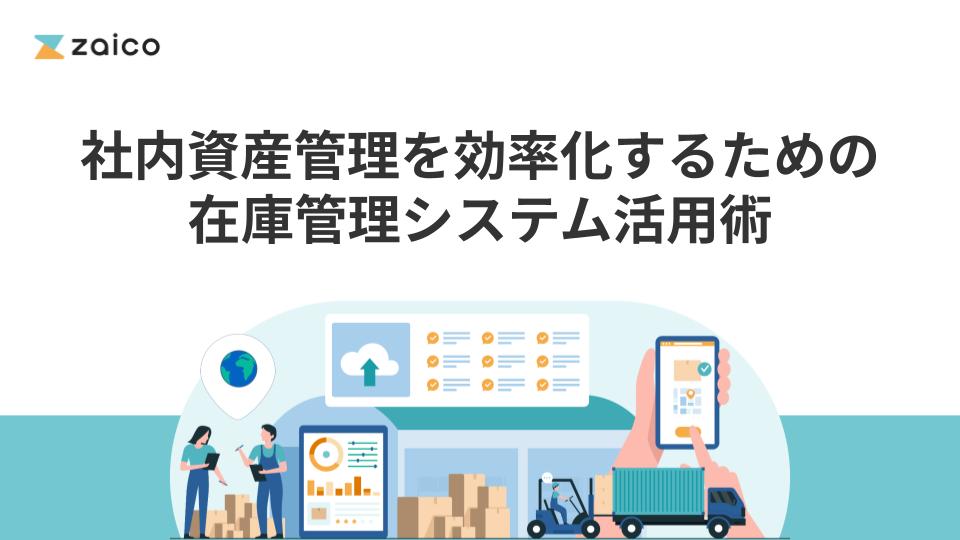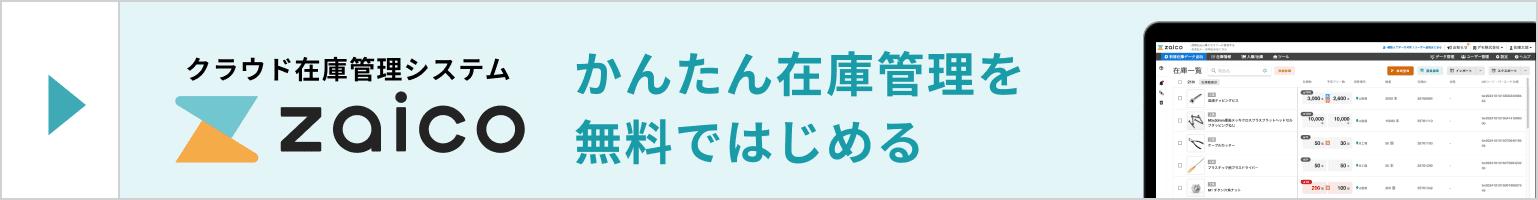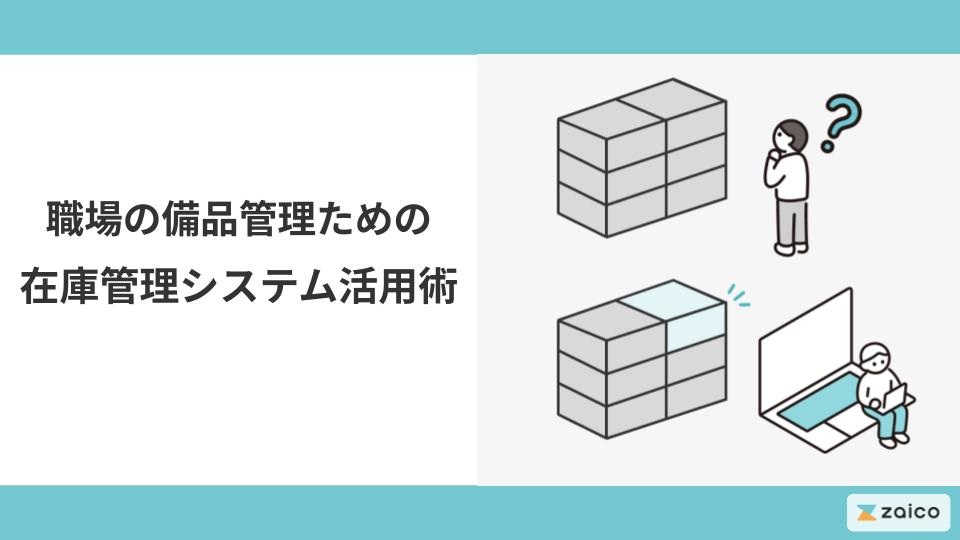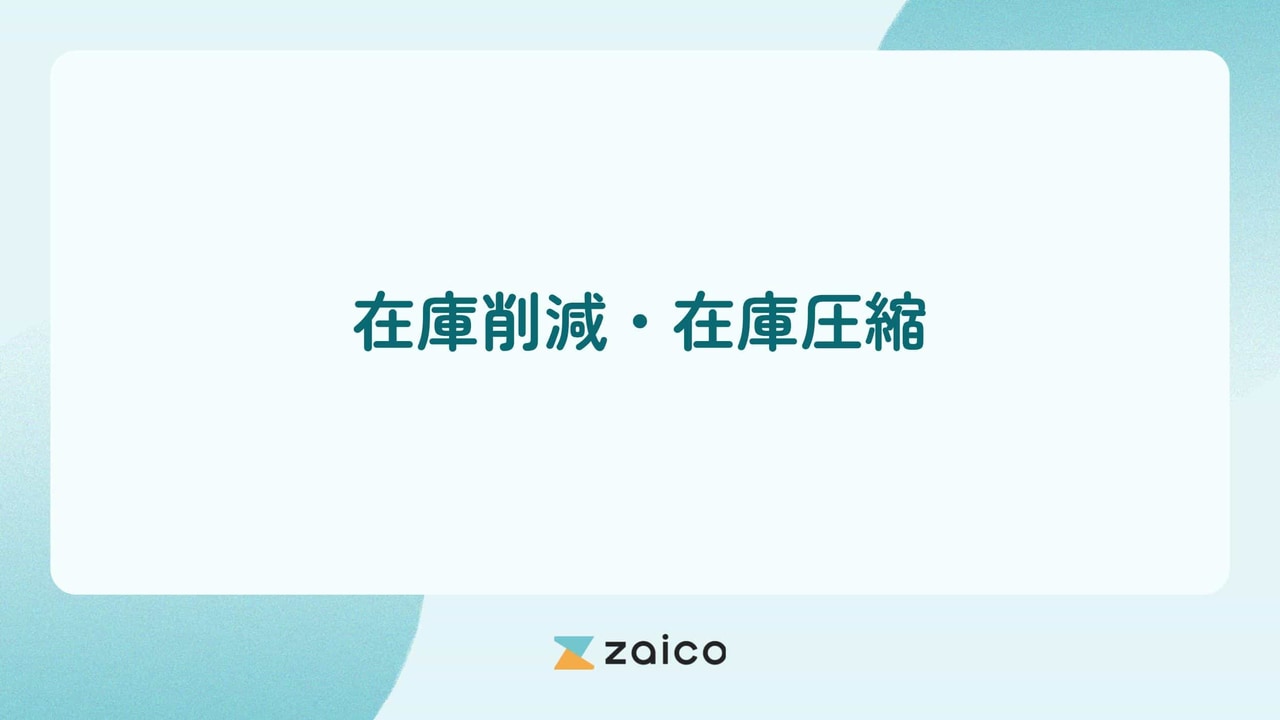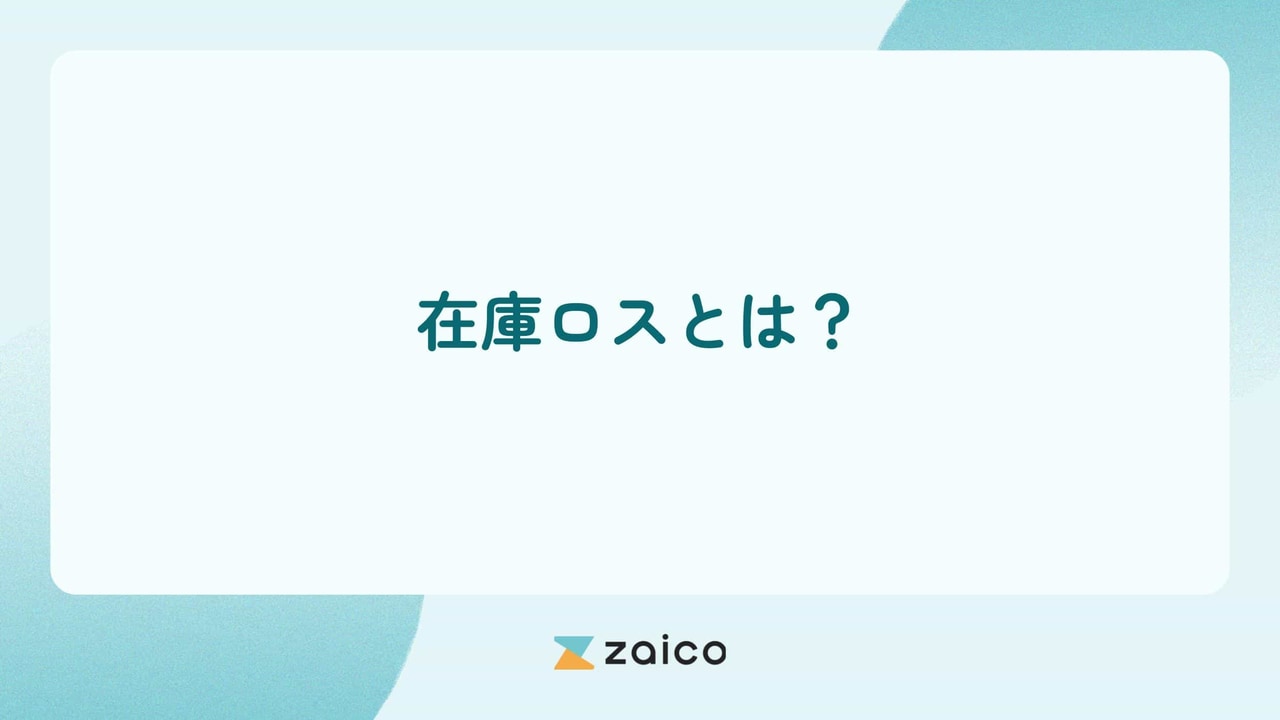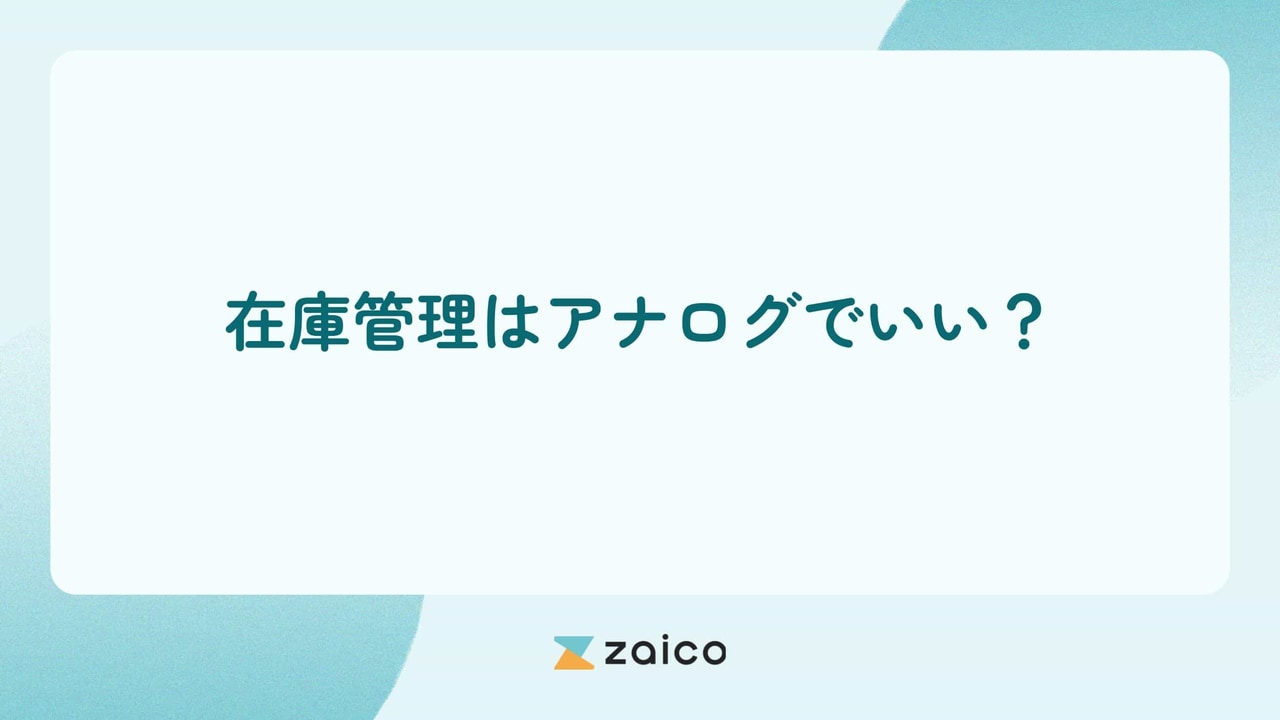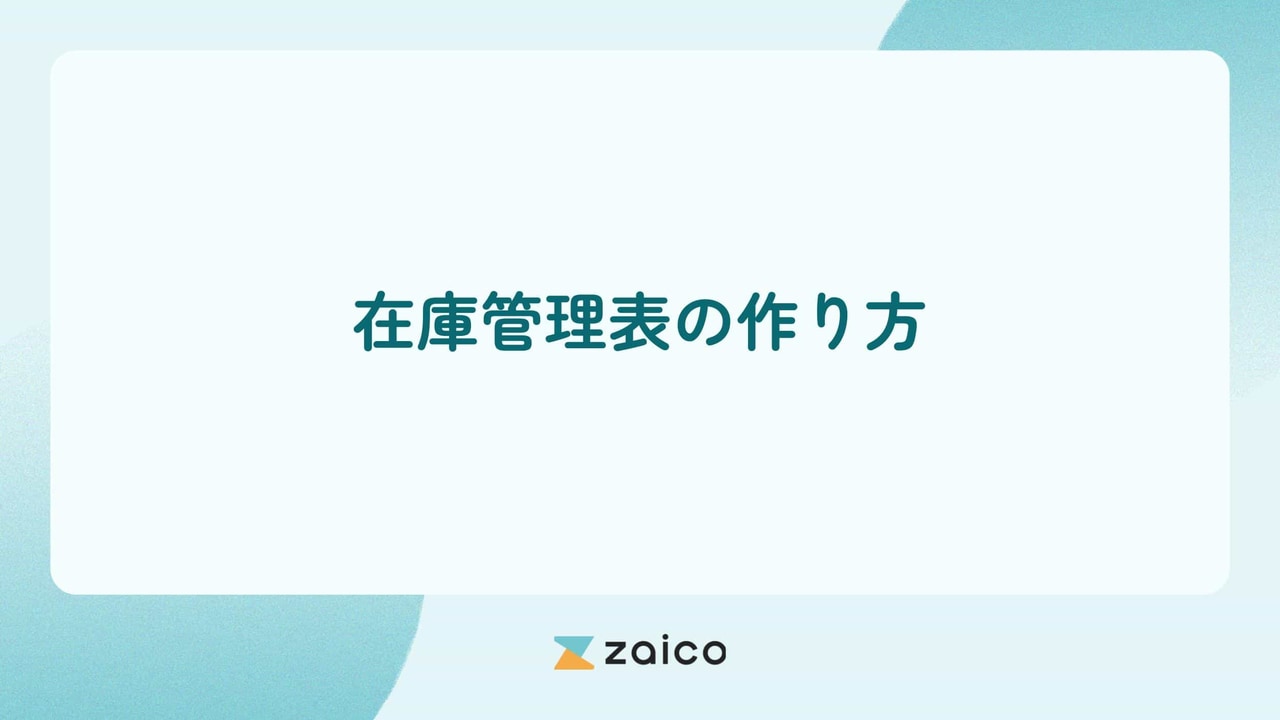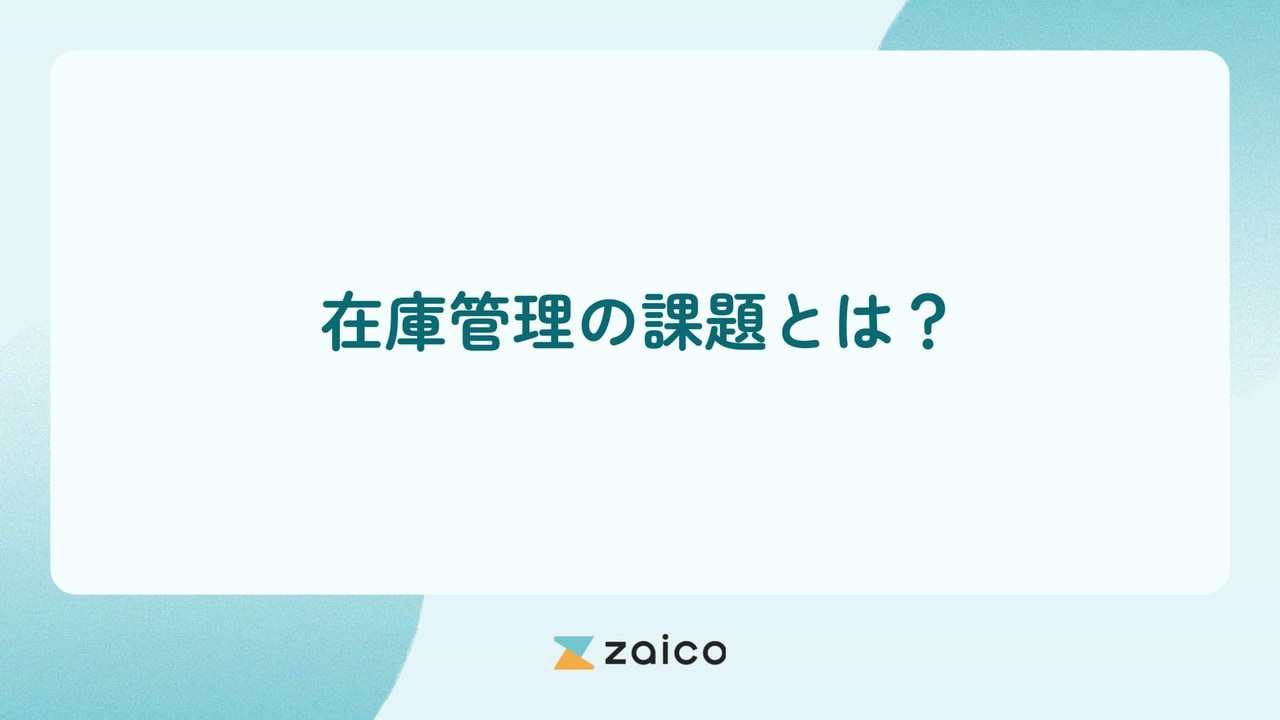日々の業務に追われる中で、備品の在庫管理は後回しにされてしまったり、適切に行えていないということもあるかもしれません。
しかし、備品の在庫管理が不適切なことで、業務の停滞や無駄なコストを発生させる大きな原因になる場合もあります。
備品の在庫管理の基本から、備品の在庫管理課題と効率化の方法、備品の在庫管理に役立つツール・システムについて確認していきましょう。
備品の在庫管理とは
備品の在庫管理とは、企業や組織内で使用する物品(=備品)の在庫を把握・調整する業務を指します。
備品とは、販売を目的としない、社内で繰り返し使用される物品のことです。
備品は、販売用の製品在庫とは管理の目的が異なります。
製品在庫は売上や利益を最大化することが目的ですが、備品在庫は「社内業務を滞りなく進める」ことが主な目的です。
そのため、備品の在庫管理を適切に行い、欠品による業務停滞や、無駄な発注によるコスト増をいかに防ぐかが求められます。
備品の在庫管理の対象物品例
備品管理の主な対象として、以下のようなものが挙げられます。
- IT機器(PC、モニター、ルーター)
- オフィス家具(デスク、椅子)
- 作業工具
- イベント用品(プロジェクター、スクリーン)
これらの備品は、ボールペンやコピー用紙のように一度使ったらなくなる「消耗品」とは区別され、比較的長期間にわたって使用されるのが特徴です。
備品の在庫管理によくある課題
備品在庫の管理は一見簡単そうに思われますが、現場ではさまざまな課題が発生します。
多くの企業が抱える備品の在庫管理によくある課題を確認していきましょう。
備品の紛失や所在不明
「どこかにあるはずなのに見つからない」これは備品在庫管理で最も多いトラブルです。
特に、複数の部署や従業員が共通で使用する備品は、返却や保管ルールが徹底されていないと所在が曖昧になりがちです。
誰がいつ使ったのかを適切に記録していないため、結果的に紛失扱いとなり、追加発注を余儀なくされるケースもあります。
欠品による業務の停滞
必要なときに備品が不足していたり、発注・補充対応が遅れたりすると業務が一時的に滞る恐れがあります。
備品の欠品は、管理担当者の備品補充忘れや、在庫数が正しく把握されていないことが主な原因です。
特に頻繁に使う備品で欠品が起こると、企業の生産性や営業機会にも大きな影響を及ぼします。
過剰在庫によるコスト増
欠品を恐れるあまり、逆に備品を持ちすぎてしまう「過剰在庫」もまた、備品在庫管理でよくある課題です。
過剰在庫は保管スペースを圧迫するだけことはもちろん、使わないまま廃棄となれば無駄なコストが発生します。
特に使用頻度が低い備品や、型落ちしやすいIT機器などは、過剰在庫が無駄になりやすい傾向があります。
備品在庫管理業務の属人化
「備品のことなら、総務部の〇〇さんに聞けば全部わかる」という状態は、一見すると頼もしい状況ですが、危険な「属人化」のサインです。
属人化とは、業務の進め方やノウハウが、特定の担当者しか把握していない状況を指します。
備品在庫管理が属人化していると、その人が異動・退職した際に業務が回らなくなるリスクがあるため注意が必要です。
備品の在庫管理を効率化する方法
備品の在庫管理課題を解決するためには、備品の在庫管理を「見える化」し、誰でもわかる仕組みに変えていくことが重要です。
備品の在庫管理を効率化する方法を確認していきましょう。
備品のカテゴリ分類・ラベリング
効率的な備品在庫管理の第一歩は、誰が見てもわかるようにするためのカテゴリ分類・ラベリングです。
備品を「IT機器」「オフィス家具」「イベント用品」などの種類や用途ごとにカテゴリ分類することで、在庫の全体像が把握しやすくなります。
また、分類した個々の備品に管理番号や資産番号を記載したラベルを貼り付けることで、個体を正確に識別できるようになり、正確な管理が可能です。
バーコードやQRコードを印字しておくと、後に紹介するデジタルツールとの連携もスムーズになります。
運用ルールの策定・徹底
モノの整理ができたら、次に行うのは「人の動き」を整えることです。
持ち出し・返却の手順や保管場所、故障・紛失時の報告フローなど、備品在庫管理に関する明確な運用ルールを策定し、それを組織全体で徹底しましょう。
ルールがなければ、せっかく整理した状態もすぐに崩れてしまいます。
また、運用ルールは作りっぱなしではなく、現場の実態に応じて定期的に見直すことも重要です。
備品の在庫管理のデジタル化
手書きの管理台帳や個人の記憶に頼る管理では、記入漏れや更新の遅れ、情報共有の難しさなどの限界があります。
これらの問題を根本から解決するのが、これまで手書きや口頭で行っていた管理をパソコンやスマートフォン上のツールに置き換える「デジタル化」です。
デジタル化によりリアルタイムな情報共有や入力ミスの削減、検索性の向上、属人化の解消など、さまざまなメリットが期待できます。
備品の在庫管理に役立つツール・システム
備品在庫管理のデジタル化を進めるにあたって、どのようなツールを選べばよいのでしょうか。
備品の在庫管理に役立つツール・システムについて確認していきましょう。
エクセルなどの表計算ソフト
多くの企業で最も手軽に始められるのが、エクセルなどの表計算ソフトを使った管理です。
すでにソフトを導入しているケースが多く、追加コストなしで始められるのが大きなメリットです。
管理番号、品名、保管場所、使用者、貸出日などの項目を並べた一覧表を作成すれば、簡易的な備品の在庫管理台帳として機能します。
一方で、入力・集計の手間や人的ミス、属人化しやすい点などのデメリットには注意が必要です。
クラウド型在庫管理システム
エクセル管理の限界を解決するのが、クラウド型在庫管理システムです。
インターネット経由で利用する在庫管理に特化したサービスで、入出庫管理や発注点管理、棚卸しサポートなど備品の在庫管理に必要な機能が搭載されています。
スマートフォンやタブレットからもアクセスできるため、現場での在庫確認や更新作業が効率化できるでしょう。
クラウドサービスで初期費用が抑えられるため、中小企業でも導入しやすい点も魅力です。
バーコード・QRコードを使った管理
備品在庫管理の精度とスピードを大幅に向上できるのが、バーコードやQRコードを活用したシステムです。
「ラベリング」の際に、管理番号をバーコードやQRコードとして印字しておき、スマートフォンや専用のリーダーで読み取ることで管理を行います。
これにより、手入力の手間とミスをなくし、貸し出しや返却、棚卸しなどの作業を正確かつスピーディーに記録できる点がメリットです。
多くの備品を扱う企業では、高い効率化の効果が期待できるでしょう。
備品の在庫管理に在庫管理システムを導入するポイント
エクセル管理の限界を超え、本格的な業務効率化を目指すなら「在庫管理システム」の導入が有効な選択肢です。しかし、ただ導入するだけでは期待する成果を得られません。
備品の在庫管理に在庫管理システムを導入する際に押さえておくべきポイントを確認していきましょう。
導入目的と必要な機能の明確化
在庫管理システム導入を成功させるための最も重要な第一歩は、「なぜ導入するのか」という目的と、「その目的を達成するために、どんな機能が必要なのか」を明確にすることです。
目的と必要な機能が曖昧なままでは、課題解決につながらなかったり、不要な機能ばかりでコストがかさんだりします。
例えば、「備品を探す時間を短くしたい」という目的であれば、「キーワード検索機能」や「使用者や保管場所の記録機能」などが必要でしょう。
目的と機能を明確化することで、適切な在庫管理システムの選択が可能になり、導入後の満足度が高まります。
現場担当者のITリテラシーへの配慮
どんなに優れた在庫管理システムを導入しても、現場が使いこなせなければ期待した効果が得られません。
システム導入の際には、実際に操作する従業員のITリテラシー(ITを使いこなす能力)を十分に考慮しましょう。
管理部門が「これは便利だ」と判断して導入を進めても、現場の従業員が「使い方がわからない」「面倒だ」と感じてしまえば、結局は古いアナログな方法に戻ってしまいます。
導入前に無料トライアルなどを活用し、複数の担当者に実際に触ってもらい、使いこなせるかを評価すると良いでしょう。
段階的な導入と定着サポート
導入した在庫管理システムを使った新しい業務プロセスを全社で一斉にスタートさせると、現場の混乱と抵抗を招く可能性があります。
混乱や抵抗をやわらげるためには、まずは限られた範囲で試験運用を行い、徐々に対象を広げていく「段階的導入」が有効です。
また、導入して終わりではなく、定着させるためのサポート体制も欠かせません。
わかりやすい操作マニュアルの作成や定期的なフォローアップなどにより、在庫管理システムが組織に定着していきます。
備品在庫管理の効率化にzaico
備品在庫管理は業界や業種を問わず、さまざまな企業に不可欠な業務です。
備品の紛失や欠品、過剰在庫などの課題は、業務の停滞やコスト増などを引き起こします。
こうした課題を防ぎ備品在庫管理を効率化するためには、ツール・システムの導入によるデジタル化が有効です。
備品在庫管理の効率化をお考えなら、「クラウド在庫管理システムzaico」をご検討ください。
zaicoは直感的な操作性で簡単に使いこなせて、パソコンやスマートフォンからいつでも・どこでも備品の状況をリアルタイムで更新・把握できます。
備品の在庫管理に在庫管理システムの活用をご検討であれば、お気軽にzaicoにご相談ください。