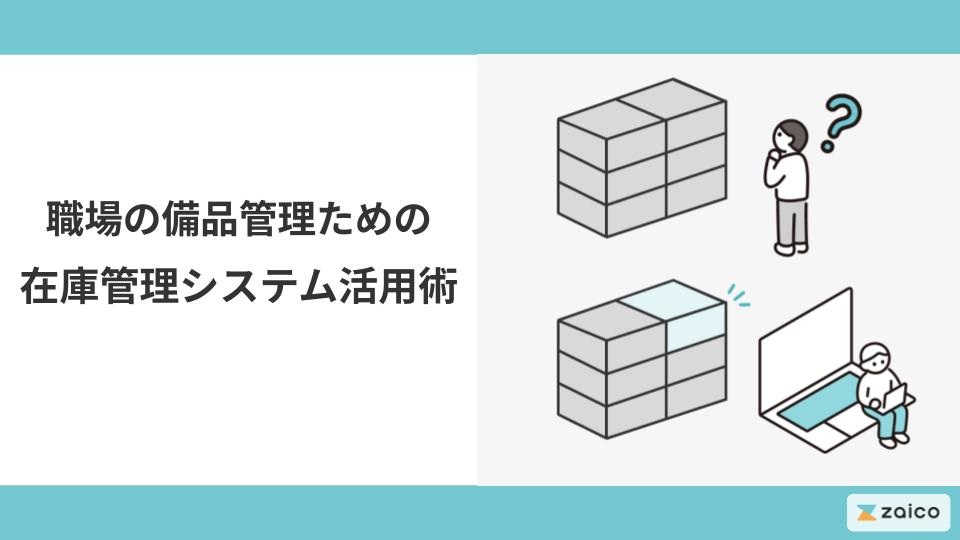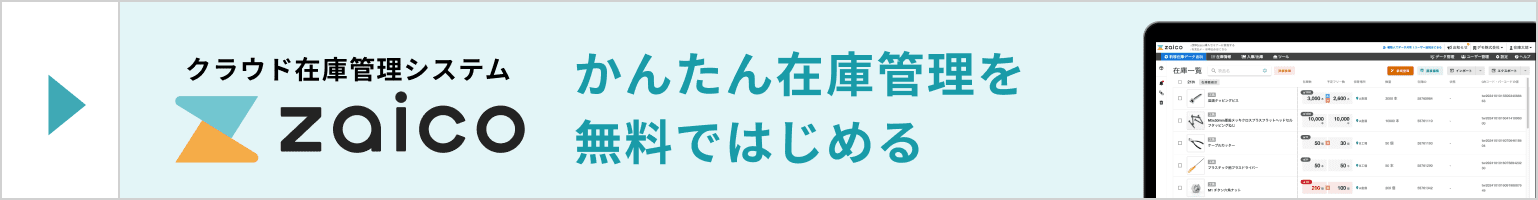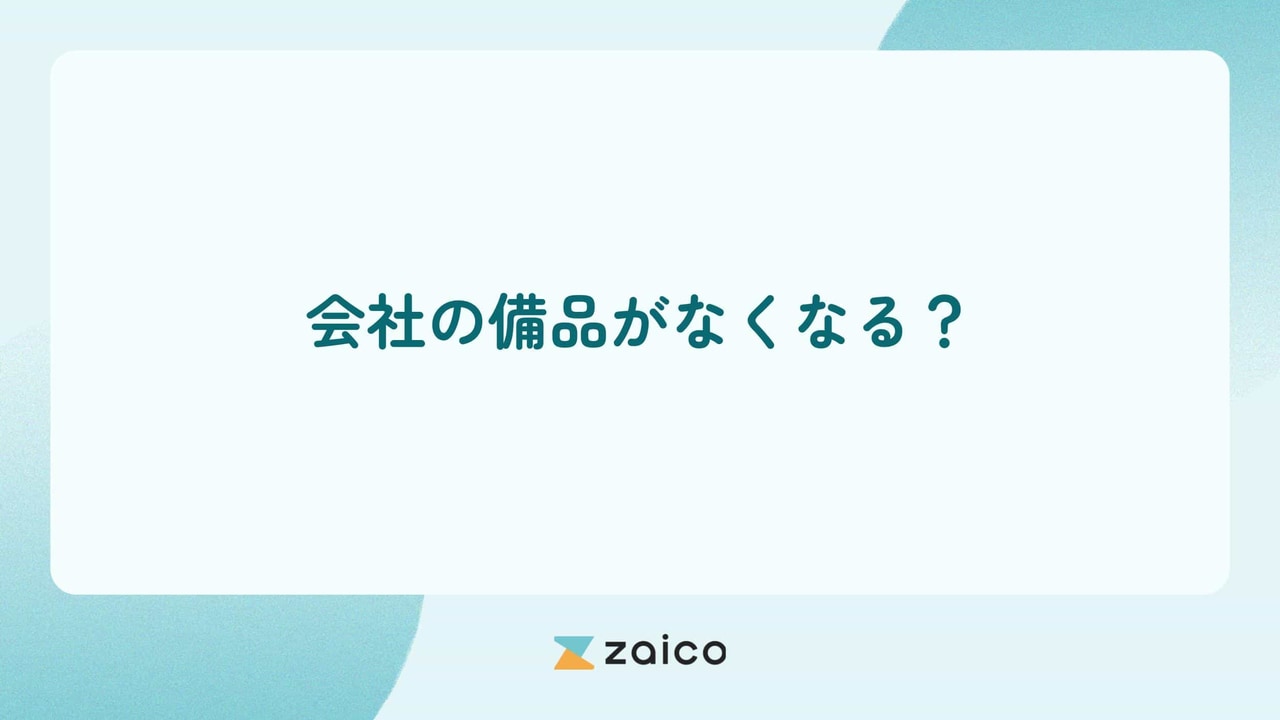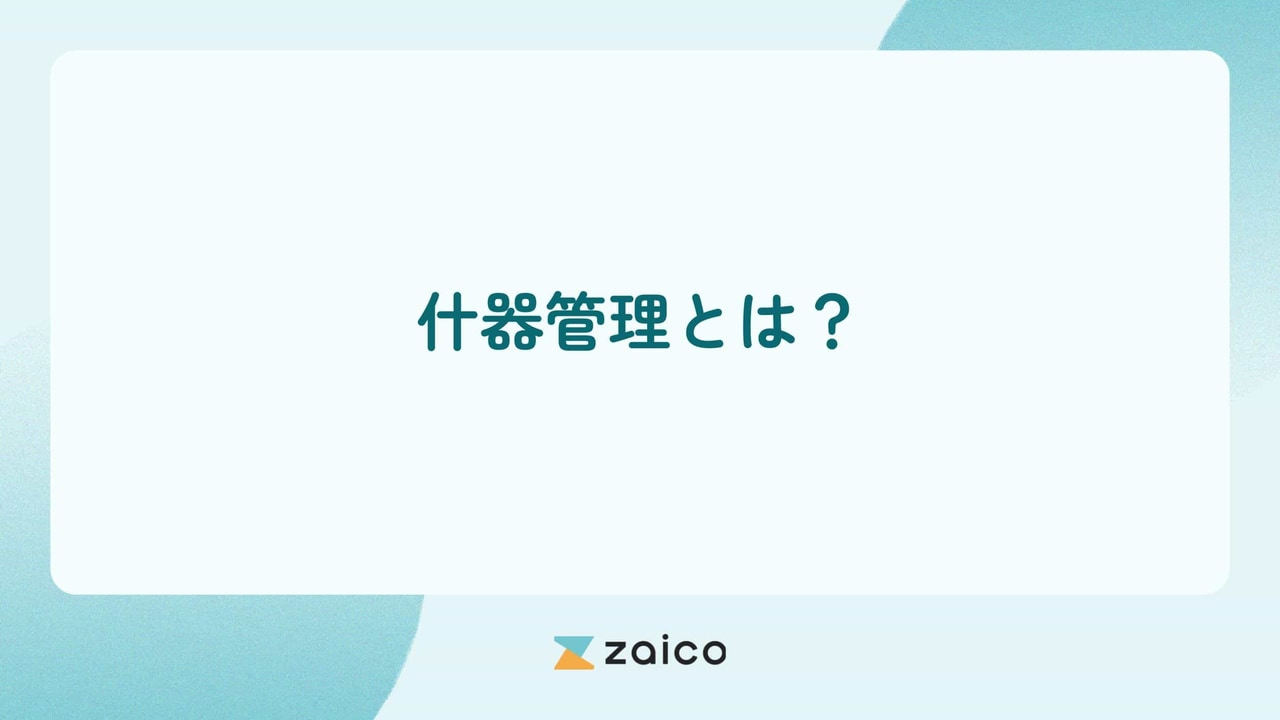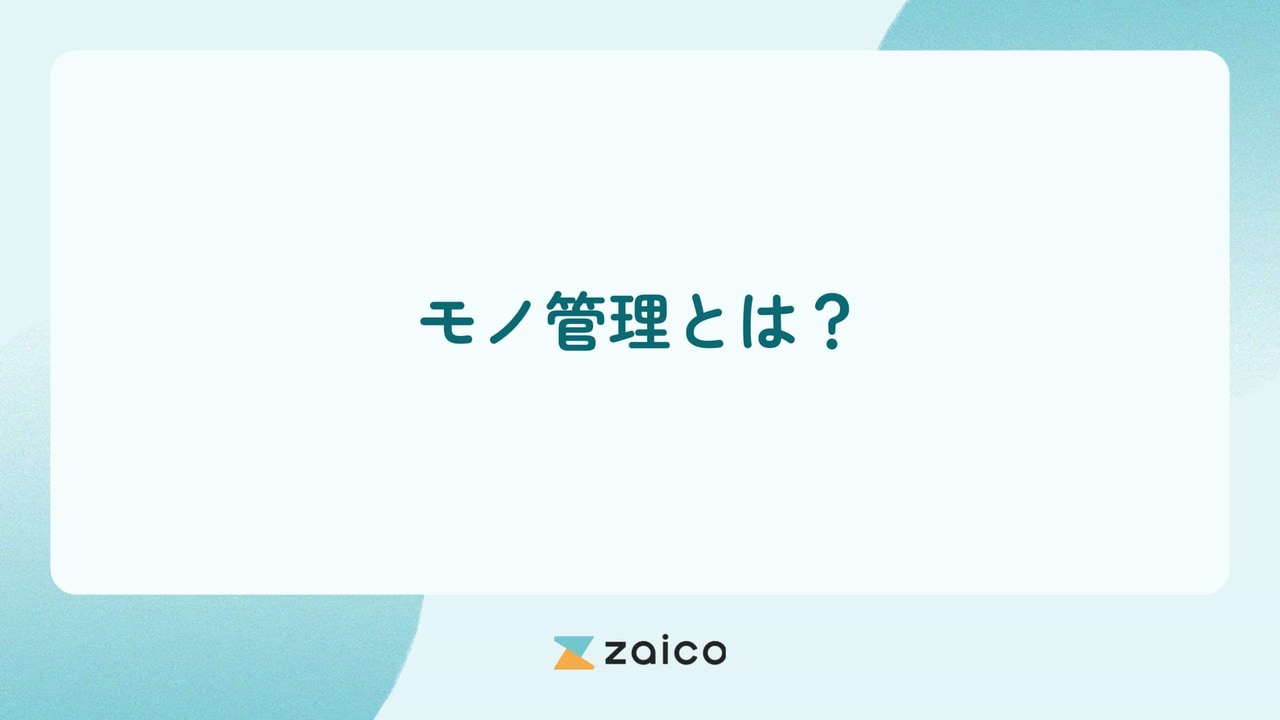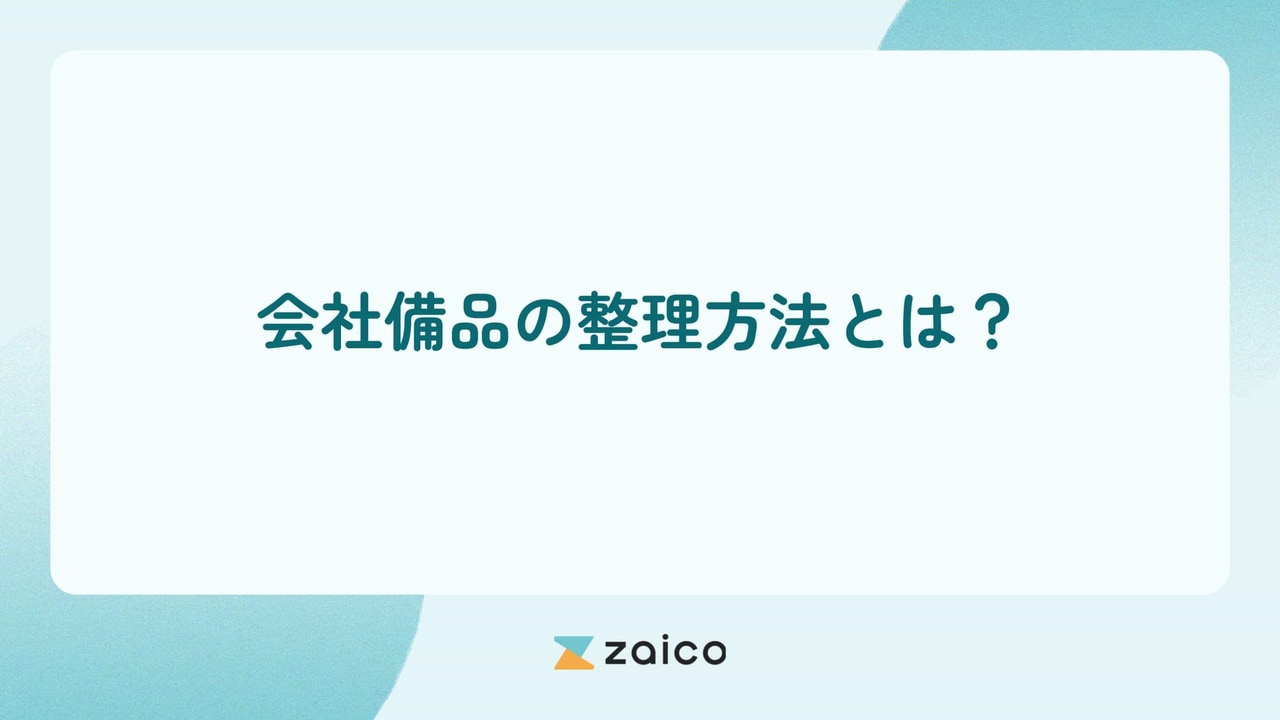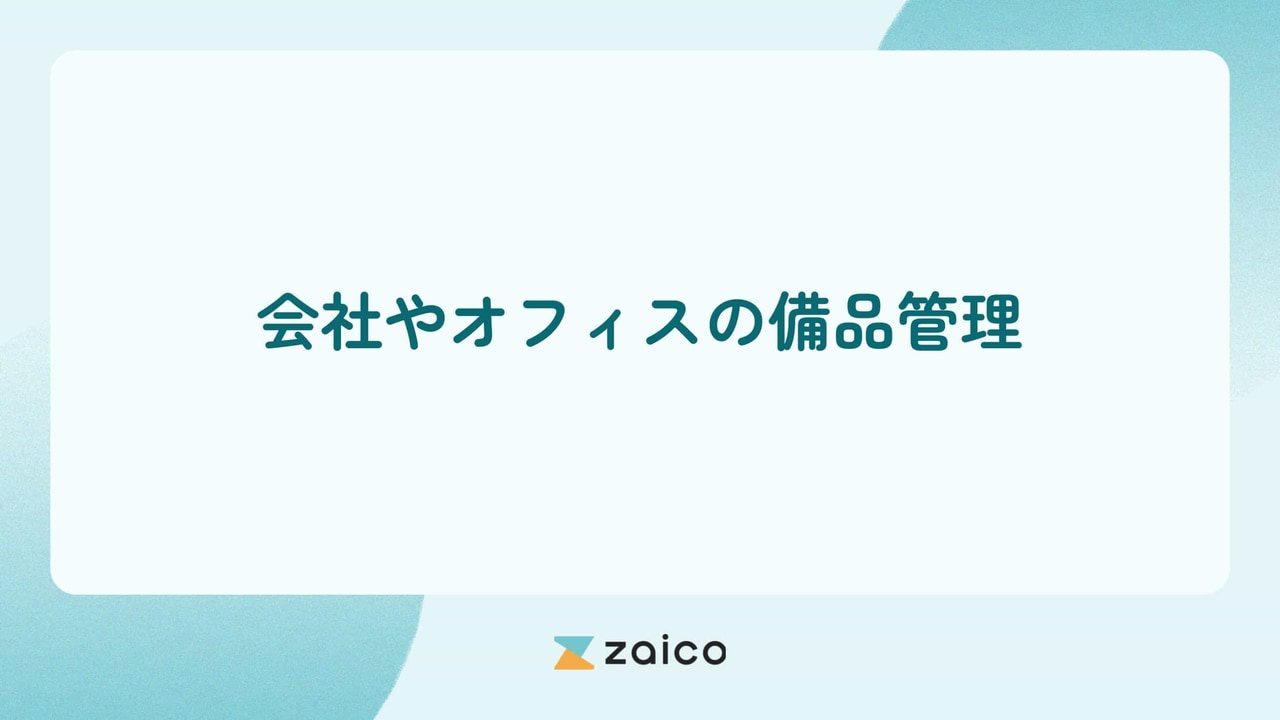オフィスでよく聞く「消耗品」と「備品」の違いはあまり意識していないかもしれません。
よく似ている消耗品と備品ですが、会計処理上では明確に区別されています。
また、在庫管理においても消耗品と備品の管理には違いがあります。
消耗品と備品の違い、会計上の消耗品と備品の違い、在庫管理の消耗品と備品の違いについて確認していきましょう。
消耗品と備品の違いとは
企業が事業活動を行う上で購入する物品は多岐にわたりますが、これらは大きく分けて「消耗品」と「備品」に分類されます。
消耗品と備品の区別は、会計処理や税務上の取り扱いにおいて重要な意味を持つものです。
また、在庫管理においても、消耗品と備品の性質の違いによって管理のポイントが異なっています。
まずは、消耗品と備品の違いや基本的な定義と、なぜ消耗品と備品の違いが重要なのかを見ていきましょう。
消耗品と備品の違い:消耗品の定義
まずは、企業活動を行う上で欠かせない「消耗品」について詳しく見ていきましょう。
消耗品とは、日常業務の中で比較的短期間に消費・使い切られる物品を指します。
一般的に取得価額が10万円未満で、耐用年数が1年未満のものが「消耗品」として扱われます。
消耗品の特徴
消耗品の特徴として、次の点が挙げられます。
- 使用期間が短い:消耗品は購入後1年以内に使い切ることが前提です
- 取得価額が低い:取得価額が通常10万円未満(中小企業などでは30万円未満の特例もあり)と比較的少額です
- 定期的に補充が必要:プリンターのインクやコピー用紙など、都度消費され、なくなれば追加購入が必要となります
- 経理処理が簡単:原則として一括して経費処理できるため、会計処理が簡素です
消耗品の具体例
消耗品の主な例は以下のとおりです。
- 事務用品: ボールペン、コピー用紙、付箋、ファイル、ホッチキスなど
- PC周辺機器: プリンターインク、トナーカートリッジ、マウスパッド、キーボードカバーなど
- 清掃用品: 洗剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ゴミ袋など
- 作業用具: 軍手、電球、乾電池、工具の一部(簡易なもの)など
消耗品の会計処理例
消耗品は、購入時に「消耗品費」や「事務用品費」などの勘定科目で一括して経費計上します。
例えば、コピー用紙1万円分を現金で購入した場合の仕訳例は以下のとおりです。
(借方)消耗品費 10,000円 / (貸方)現金10,000円
原則として、購入した時点で費用計上するため、期末に在庫として残っていても棚卸資産として計上する必要はありません。
ただし、期末に未使用の消耗品が大量にある場合は、「消耗品(資産)」として計上し、翌期に使用した分を費用に振り替える処理が必要になることもあります。
消耗品と備品の違い:備品の定義
次に、「備品」について詳しく見ていきましょう。
備品は、企業が事業活動を行う上で長期にわたって使用することを目的として購入する物品のことです。
消耗品とは異なり、その価値が比較的長く持続し、会社の資産として備品は扱われます。
備品の特徴
備品には、以下のような特徴があります。
- 耐用年数が長い:一般的に、購入後1年以上使用されると見込まれるものです
- 取得価額が高い:取得価額は通常10万円以上と比較的高額です
- 固定資産として管理:原則として「器具備品」や「什器備品」として固定資産に計上する必要があります
- 減価償却が必要:複数年に渡って費用配分するため、減価償却を行います
備品は資産として管理されるため、台帳による管理が必要で、取得から除却まで記録を保持することが求められます。
備品の具体例
備品の主な例は以下のとおりです。
- 事務機器: パソコン、プリンター、複合機、シュレッダー、プロジェクターなど
- 什器・家具: デスク、椅子、書庫、キャビネット、応接セット、会議用テーブルなど
- 家電製品: 冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、テレビなど(事業用として使用されるもの)
- 工具・器具: 専用工具、測定器、実験器具など(比較的高価で長期使用するもの)
備品の会計処理例
備品は原則として購入時に「固定資産」として計上し、毎年少しずつ減価償却します。
例えば、12万円のパソコン(耐用年数4年)を現金で購入した場合、購入時の仕訳例は以下のとおりです。
(借方)工具器具備品 120,000円 / (貸方)現金 120,000円
その後、4年間にわたって毎年3万円ずつ、以下のように減価償却費として計上します。
(借方)減価償却費 30,000円 / (貸方)工具器具備品減価償却累計額 30,000円
このように、備品は複数年にわたって費用化されるため、企業の財務状況をより正確に反映できます。
消耗品と備品の違い:区別のポイントは耐用年数と取得価額
消耗品と備品の違いを理解し、区別する上で最も重要なポイントをまとめると、「耐用年数」と「取得価額」です。
まず耐用年数は、1年未満で消費される物品は消耗品、1年以上使用可能な物品は備品として分類されます。
次に取得価額では、10万円未満は消耗品、10万円以上は備品とするのが一般的です。
ただし、中小企業などでは30万円未満の減価償却資産は、年間300万円まで一時償却が可能な特例があります。
正確な分類が難しい場合は、税理士や会計士などの専門家に相談するのがおすすめです。
消耗品と備品の違い:在庫管理の違い
消耗品と備品の違いは、会計処理だけでなく、日々の在庫管理においても異なるアプローチが求められます。
消耗品と備品の特性を理解し、適切な管理方法を実践することで、無駄なコストを削減し、業務効率を向上させることが可能です。
在庫管理における消耗品と備品の違いを見ていきましょう。
消耗品の在庫管理の特徴
消耗品の在庫管理で重要なポイントは、「残量管理」と「補充タイミングの見極め」です。
消耗品は以下のような特徴があるため、常時一定数を維持し、不足がないよう計画的な補充を行う必要があります。
- 回転率が高い: 消費サイクルが速いため、在庫切れを起こしやすい一方で、過剰な在庫はデッドストックになりやすいという特性があります
- 単価が低い: 個々の単価が低いため、一つひとつの物品を厳密に管理するよりも、全体としての在庫水準を適切に保つことが重視されます
- 管理の簡素化: 詳細な入出庫記録よりも、補充のタイミングや発注量の最適化に重点が置かれます
消耗品の在庫管理の目的は、「必要な時に必要なものが手元にある状態を維持しつつ、過剰な在庫を持たない」ことです。
これにより、保管スペースの有効活用や、消耗期限切れによる廃棄ロスの削減が図れます。
備品の在庫管理の特徴
一方で、高額で動きの少ない備品の在庫管理では、「物品ごとの資産管理」が必要です。
主な特徴は以下のとおりです。
- 回転率が低い: 使用期間が長いため、頻繁な入出庫は発生しません
- 単価が高い: 個々の単価が高いため、紛失や破損による損失は企業にとって大きなダメージとなります
- 資産としての管理: 固定資産としての性格を持つため、購入から廃棄までのライフサイクル全体を詳細に管理する必要があります
備品は、定期的な現物確認による実地棚卸を実施し、資産台帳と実際の保有状況の整合性を確認します。
消耗品も備品も管理には在庫管理システムが良い理由
消耗品と備品では、その特性から在庫管理のアプローチが異なりますが、共通していえることは、手作業での管理には限界があるということです。
特に物品の種類が増え、管理する量が多くなるにつれて、人的ミスのリスクや作業の非効率さが課題になります。
そこで、消耗品、備品に関わらず、在庫管理システムの導入が有効です。
在庫管理システムの導入により、以下のようなメリットが得られます。
- リアルタイムな在庫状況の把握
- バーコードやQRコードによる入出庫・棚卸の効率化
- 適切な発注タイミングの通知
- 複数拠点のデータの一元管理
- 会計システムとの連携
在庫管理システムは、消耗品の定数管理から備品の個体管理まで、それぞれの物品の特性に合わせた柔軟な設定が可能です。
これにより担当者の負担を軽減し、在庫データの精度向上が期待できます。
消耗品と備品の違いはあっても在庫管理はzaico
消耗品と備品は混同されがちですが、税法上は耐用年数や取得価額によって明確に区別されています。
在庫管理においては、消耗品は継続的な消費管理と適正在庫の維持、備品は個別資産管理と減価償却対応が重要なポイントとなります。
消耗品と備品の違いを踏まえた上で、効率的な在庫管理を実現するために、在庫管理システムの活用が有効です。
消耗品と備品の効率的な在庫管理をお考えなら、「クラウド在庫管理システムzaico」をご検討ください。
zaicoは、バーコードやQRコードによる入出庫管理やリアルタイムでの在庫数量把握、発注点管理機能で、消耗品や備品の効率的な管理を実現します。
スマートフォン・タブレット向けアプリも提供しており、直感的な操作で誰でも簡単に使えます。
消耗品と備品の在庫管理に在庫管理システムの活用をご検討であれば、お気軽にzaicoにお問い合わせください。