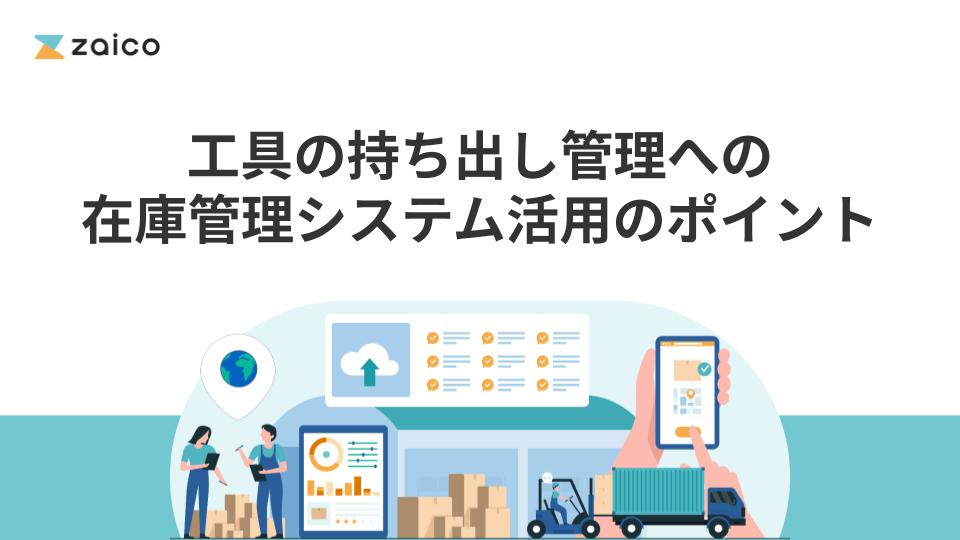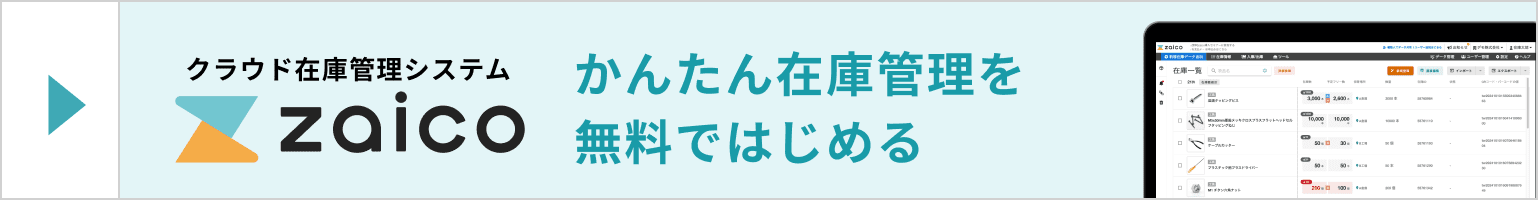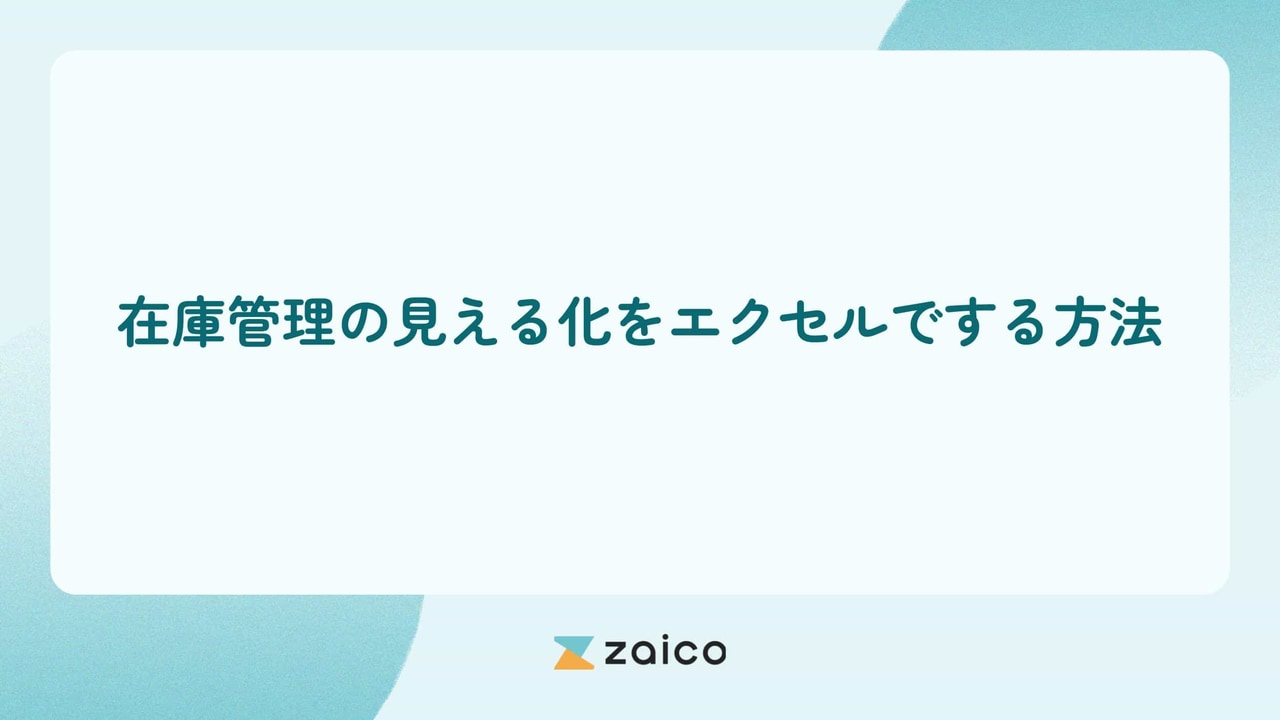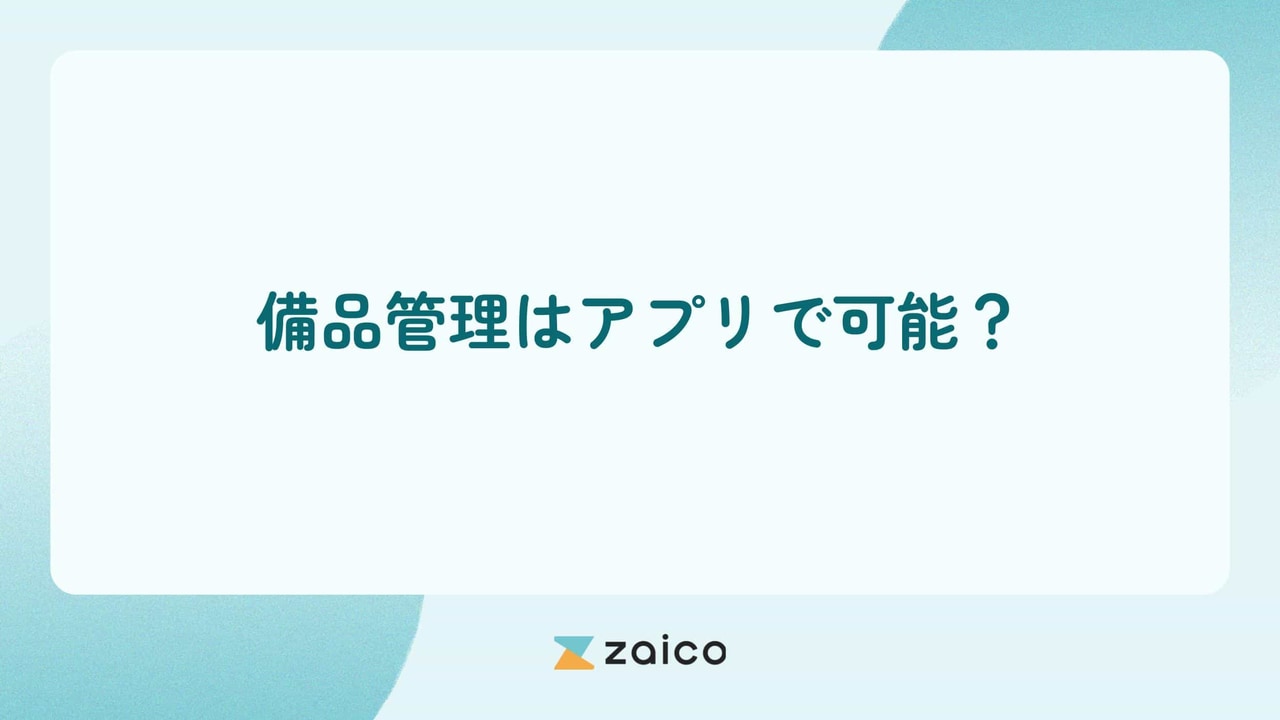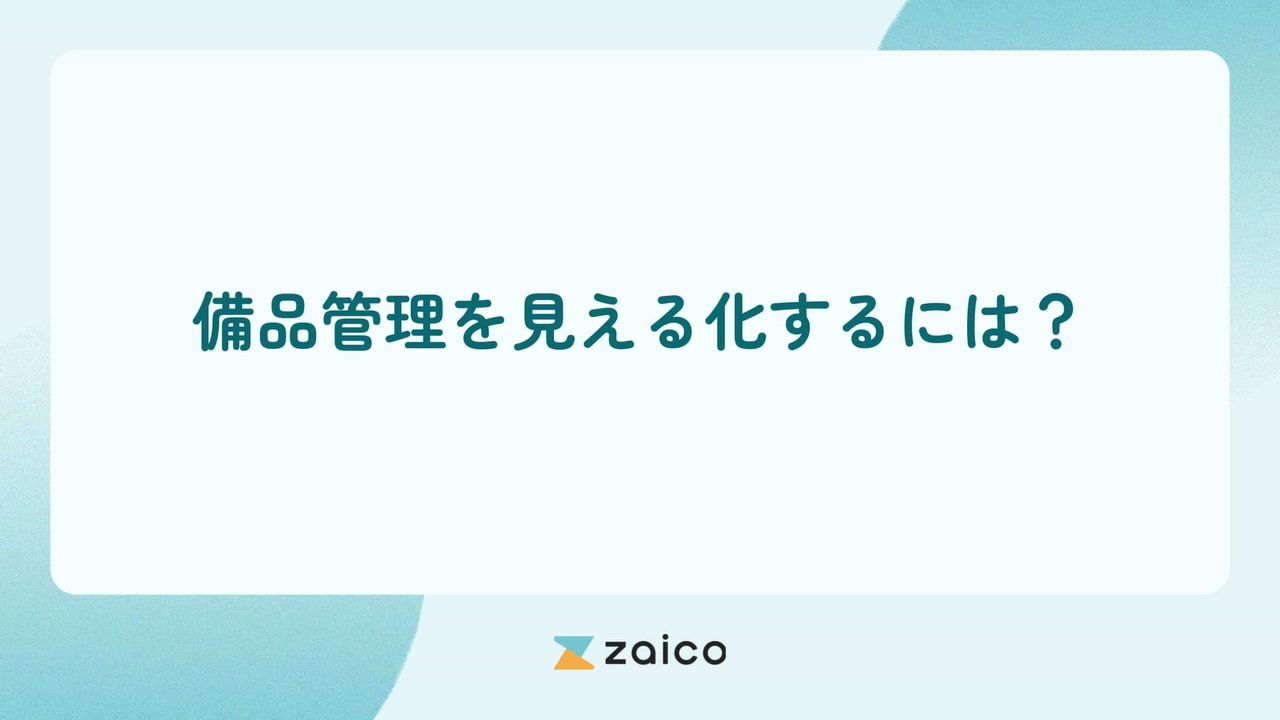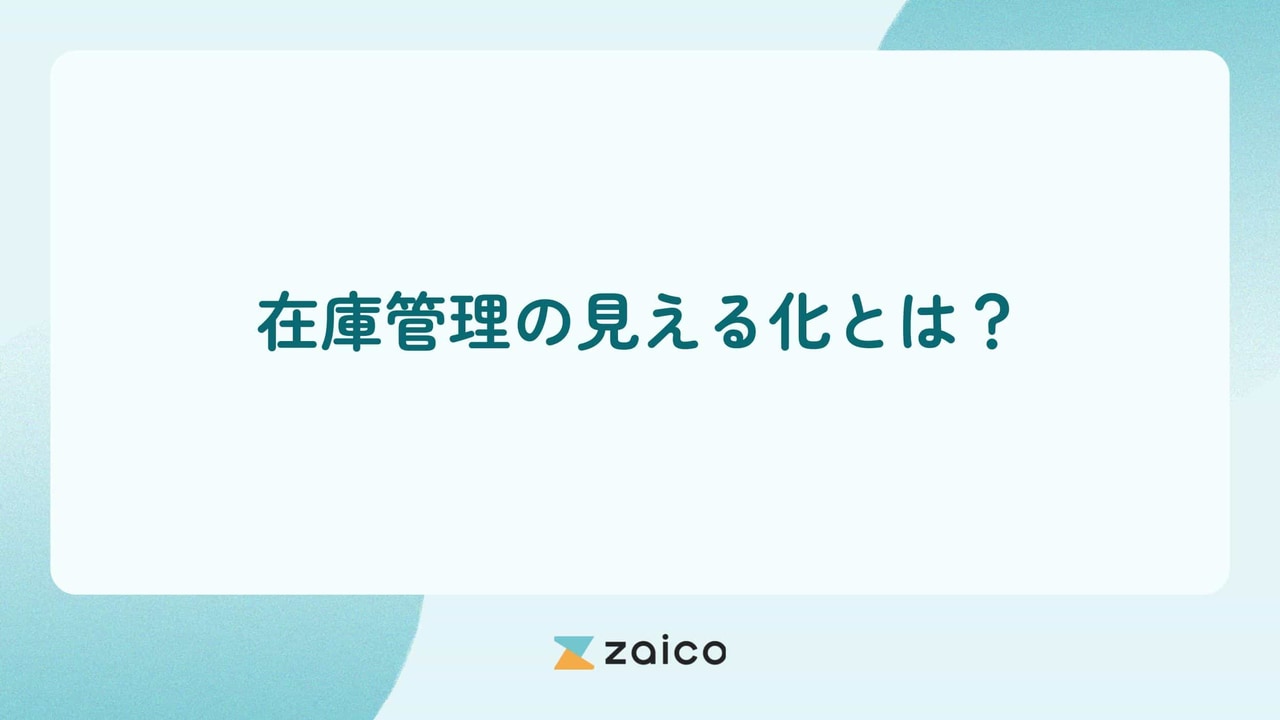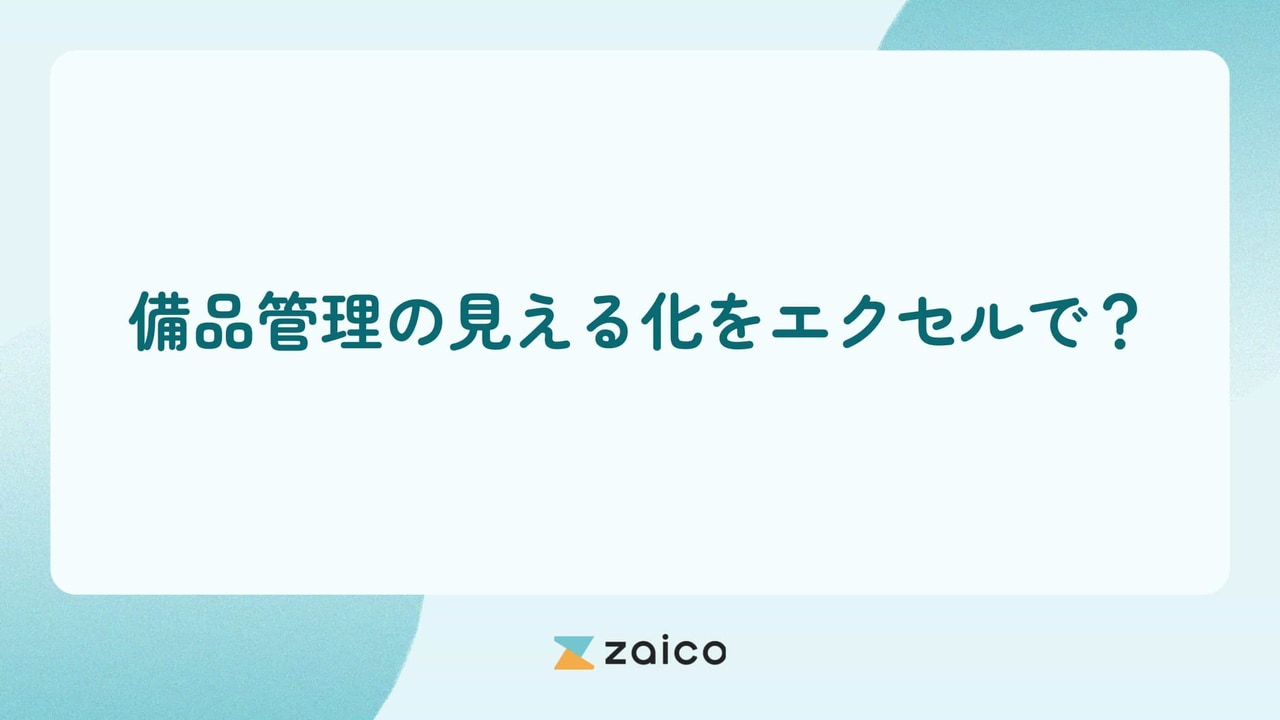製造業や建設業の現場で、工具がない、工具はどこに行ったなどの会話が日常的に交わされていませんか。
工具を探す時間は生産性を低下させ、見つからなければ新たな購入コストが発生します。
このような工具管理の課題を解決する鍵が「工具管理の見える化」です。
工具管理の見える化とは何かから、工具管理を見える化するメリット、具体的な工具管理の見える化の方法について確認していきましょう。
工具管理の見える化とは
「工具管理の見える化」とは、「いつ、どこで、誰が、どの工具を、どのような状態で」使用しているのかを、関係者全員が把握できるようにする取組です。
工具管理の見える化は、単に工具の数を把握するだけでなく、その所在やステータス(使用中、保管中、修理中など)を明確にすることが重要です。
工具管理の見える化をすることで業務や管理の効率化に効果的にはなりますが、工具管理の見える化ができていない状態には、さまざまなリスクが潜んでいます。
工具管理が見える化されないリスク
工具管理が見える化されていない現場では、多くの問題が発生しやすくなります。
最も代表的なのが、工具を探す時間の発生による生産性の低下です。
必要なときに工具が見つからなければ、作業が中断してしまいます。
また、見つからないために同じ工具を重複して購入してしまい、無駄なコストがかさむことになるでしょう。
さらに、工具の状態が把握できていないと、メンテナンス不足のまま使用され、製品の品質低下や事故につながるケースもあります。
このように、工具管理が見える化されていないことは、多くのリスクを招く問題です。
工具管理を見える化するメリット
工具管理の見える化には、先に挙げたリスクを回避し、企業にさまざまなメリットをもたらします。
工具の見える化で得られるメリットを確認していきましょう。
工具の所在や使用状況が把握でき業務を効率化できる
工具管理を見える化する大きなメリットは、業務効率の向上です。
工具の保管場所や現在の使用者、返却予定日などが一目瞭然になれば、「探す」という非生産的な時間をゼロに近づけられます。
作業者は、必要な工具をすぐに見つけて業務に取り掛かることができ、貸し出しや返却のプロセスもスムーズになるでしょう。
これにより、作業の段取りが組みやすくなり、工場全体の生産性向上につながります。
工具の行方不明や紛失を防止できる
「いつの間にか工具がなくなっていた」という経験は、多くの現場であるのではないでしょうか。
見える化は、こうした工具の行方不明や紛失の防止にも大きな効果を発揮します。
誰がいつ工具を持ち出したのか、履歴がデータとして記録されるため、返却忘れや置き忘れの特定が可能です。
これにより、「誰が最後に使ったかわからない」という状況がなくなり、個々の従業員の管理意識も向上します。
工具のメンテナンスや交換のタイミングがわかる
工具は使うほどに摩耗し、劣化していくものです。
見える化によって、個々の工具の使用回数や使用期間を正確に記録することで、最適なタイミングでメンテナンスや交換を行うことが可能になります。
例えば、ドリルの刃や砥石のような消耗品は使用回数に応じた交換時期の判断が不可欠です。
これらの情報をシステムで管理し、時期が来たらアラートを出すように設定すれば、メンテナンス漏れを防ぎ、常に工具を最良の状態で使用できるようになります。
工具管理の属人化を防ぎ誰でも管理しやすくなる
見える化は、特定のベテラン従業員の頭の中にしか工具の保管場所や管理ルールがない、という「属人化」の解消にも有効です。
属人化には、担当者が不在だったり、退職してしまったりすると、途端に工具管理が機能不全に陥るリスクがあります。
工具管理の見える化により、経験の浅い従業員や他部署からの異動者でも、同じように工具を管理することが可能になります。
担当者の引き継ぎもスムーズになり、組織として安定した管理体制を構築できるでしょう。
工具管理を見える化するためのステップ
工具管理の見える化を成功させるためには、やみくもにツールを導入するのではなく、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。
工具管理の見える化を実現するための基本的なステップを確認していきましょう。
現状把握と課題の明確化
最初のステップは、自社の工具管理の現状を正確に把握することです。
まずは、保有している工具をリストアップし、工具の種類や数量、保管場所、状態などを整理します。
また、現場の従業員へのヒアリングなどにより紛失頻度や探す時間などの課題を洗い出しましょう。
これにより、見える化によって解決すべきポイントが明らかになります。
目標設定と見える化の範囲決定
次に、現状の課題をもとに、具体的な目標を設定します。
例えば、「工具の探索時間を月間10時間削減する」「工具の年間紛失コストを50%削減する」など、測定可能な数値目標を立てることが重要です。
また、全工具か特定カテゴリかなど、見える化の対象とする範囲を決めましょう。
予算と期待効果のバランスを考慮し、最適な範囲設定を行うことが成功の鍵となります。
適切なツール・システムの選定
目標と範囲が決まったら、それを実現するためのツールやシステムを選定します。
手軽に始められるエクセルから、専門的な機能を持つクラウド在庫管理システム、より高度なIoTを活用したシステムまでさまざまです。
導入前にトライアルを実施し、現場への適合性を確認すると良いでしょう。
機能やコスト、導入のしやすさなどを総合的に比較検討して判断することが重要です。
運用ルールの策定と周知
優れたシステムを導入しても、それを使うためのルールが不十分だと正しく運用されません。
「誰が、いつ、どのデータ入力するのか」、「貸し出し・返却はどのような手順で行うのか」、「紛失・破損時は誰に報告するのか」など、具体的な運用ルールを策定します。
策定したルールは、説明会やマニュアルなどで関係者全員に周知徹底し、全員の理解と協力を得ることが成功の鍵です。
導入後の効果測定と継続的な改善
工具管理の見える化は、システムを導入し、運用を開始したら終わりではありません。
定期的に、設定した目標がどの程度達成できているかを測定・評価し、改善していくことが重要です。
「ルールが複雑で守られていない」「システムのこの機能が使いにくい」などの現場の声に耳を傾け、運用ルールやシステムの設定を見直しましょう。
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の「PDCAサイクル」を回し続けることで、工具管理レベルの継続的な向上が実現します。
工具管理を見える化するツール・システム
工具管理の見える化を実現するには、さまざまなツール・システムがあります。
手軽なものから先進的なものまで、現場の規模に合わせて選びましょう。
工具管理を見える化するツール・システムについて確認していきましょう。
エクセル
エクセルによる見える化は、多くの企業で導入されており、追加コストなしで手軽に始められるツールです。
工具リストの作成や簡単な数量管理であれば、多くの人が使い慣れた操作で対応できます。
ただし、手入力が基本のため入力ミスも発生しやすく、管理が属人化しやすいというデメリットもあります。
小規模な現場やツール導入の初期段階に適しているでしょう。
クラウド在庫管理システム
クラウド在庫管理システムは、インターネット経由で利用する在庫管理に特化したシステムです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスからいつでもどこでも最新の情報にアクセスでき、リアルタイムで情報を共有できます。
バーコードやQRコードの読み取りに対応したものが多く、入力の手間とミスの大幅な削減が可能です。
工具管理の課題を本格的に解決したい場合には有効な選択肢といえるでしょう。
IoTセンサー
IoT(Internet of Things:モノのインターネット)技術を活用した、より高度な見える化システムです。
RFIDタグやビーコンなどの小型のセンサーを工具に取り付けることで、リーダーをかざしたり、ゲートを通過したりするだけで、複数の工具情報を一括で読み取り、位置情報を自動で把握できます。
手作業でのスキャンすら不要になり高度な自動化・効率化を実現できますが、導入コストが高額になりがちな点に注意が必要です。
工具管理の見える化にzaico
工具を探す無駄な時間、度重なる紛失、不十分なメンテナンスなどの課題は、「見える化」によって解決できます。
工具の所在・使用履歴・メンテナンス情報などを一元管理して見える化することで、業務効率化や紛失防止、属人化の防止が可能です。
見える化を成功させるためには、自社の課題解決に適したツール・システムの導入が欠かせません。
工具管理の見える化をお考えなら、「クラウド在庫管理システムzaico」をご検討ください。
zaicoは、直感的な操作性と豊富な機能により、工具管理の見える化を強力にサポートします。
工具管理の見える化に在庫管理システムの利用をご検討いただける場合は、お気軽にzaicoにご相談ください。