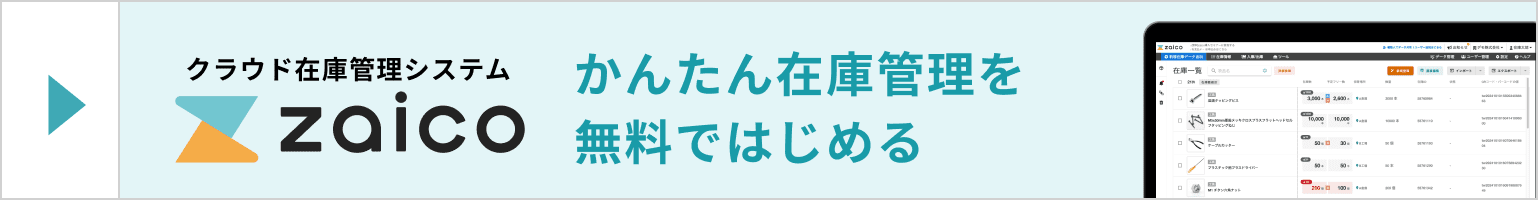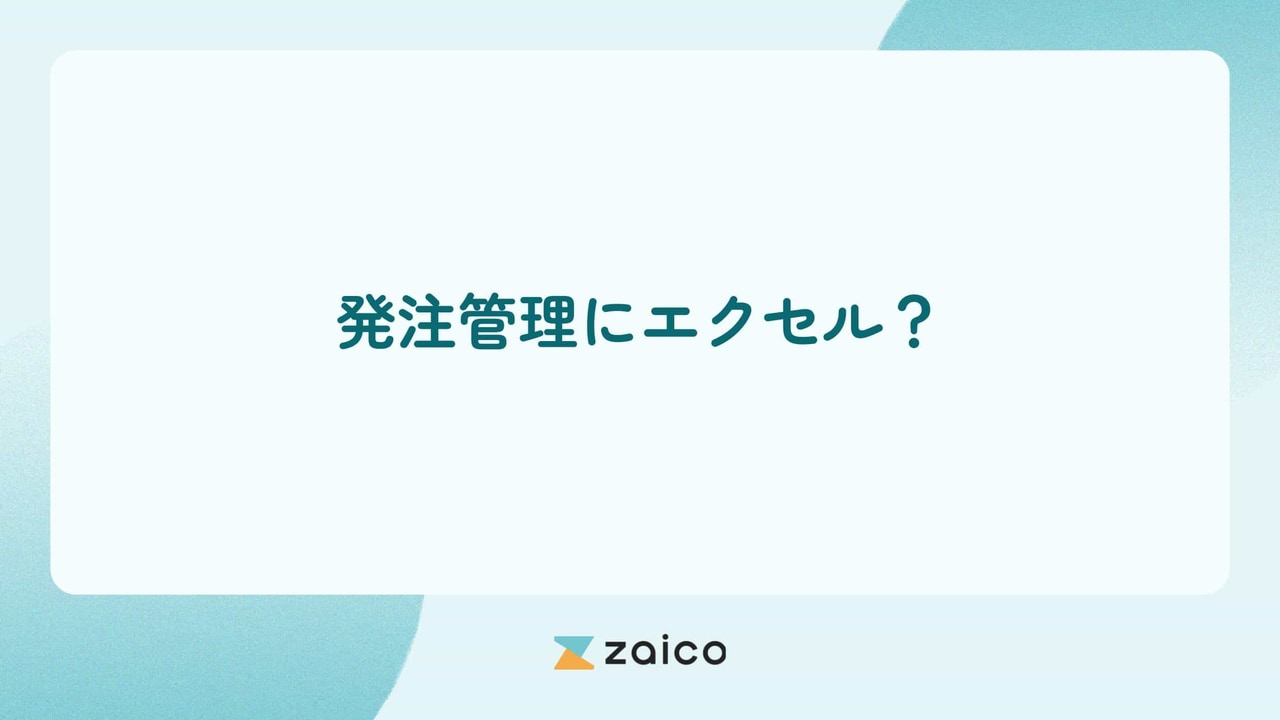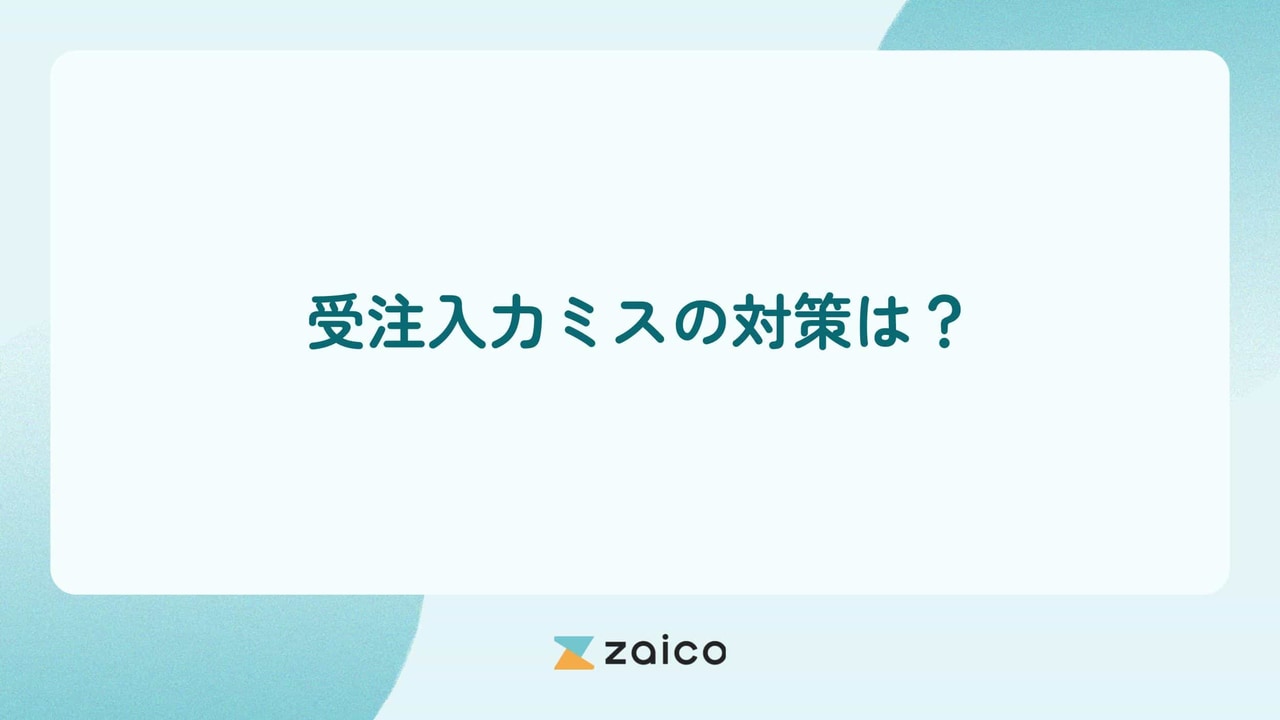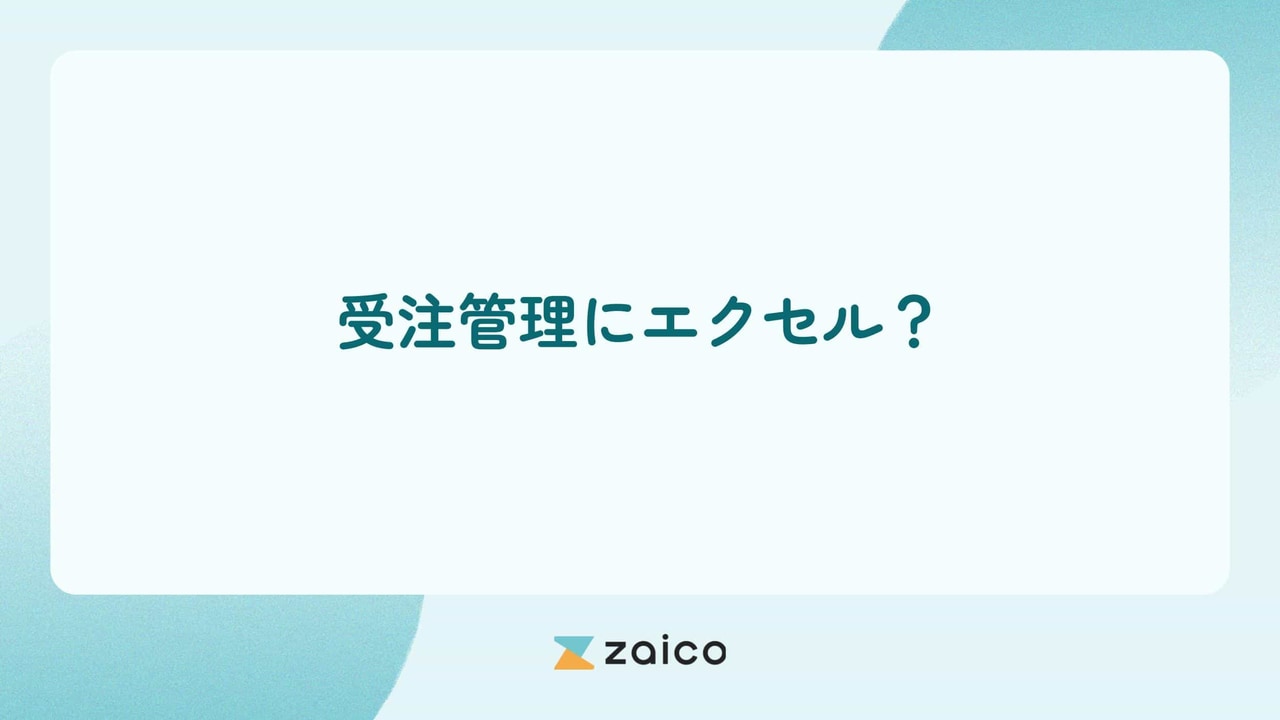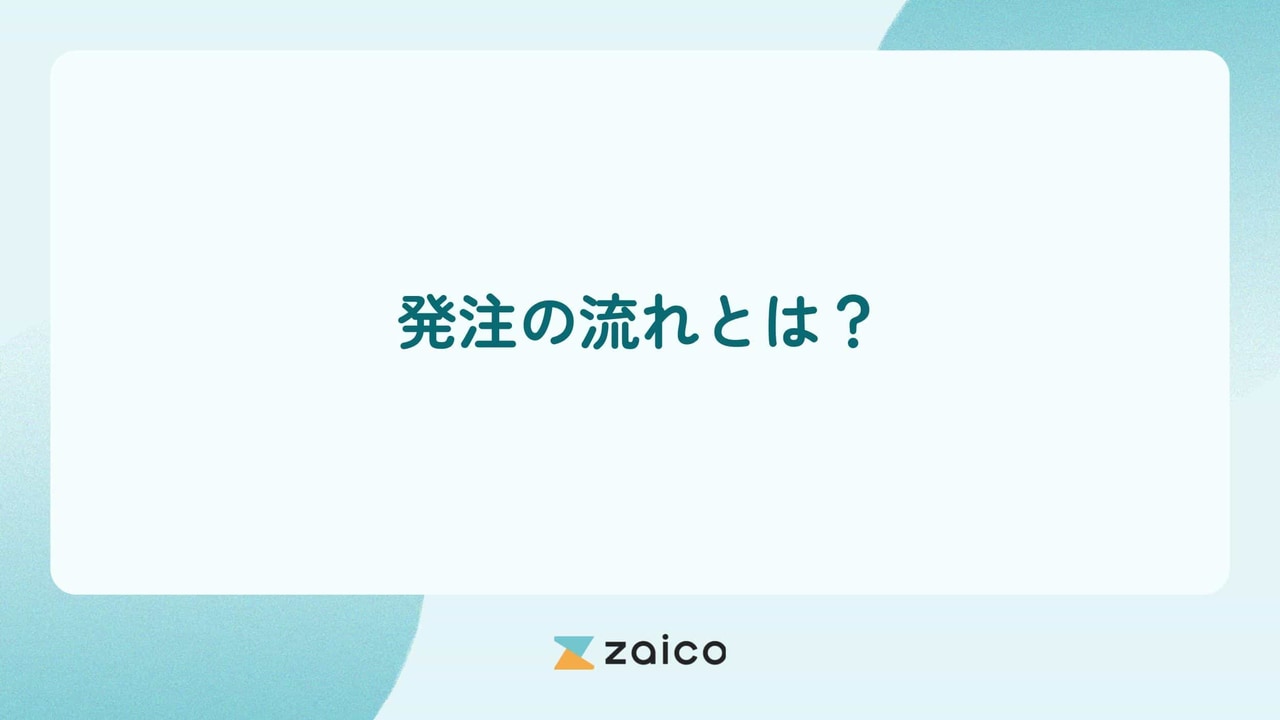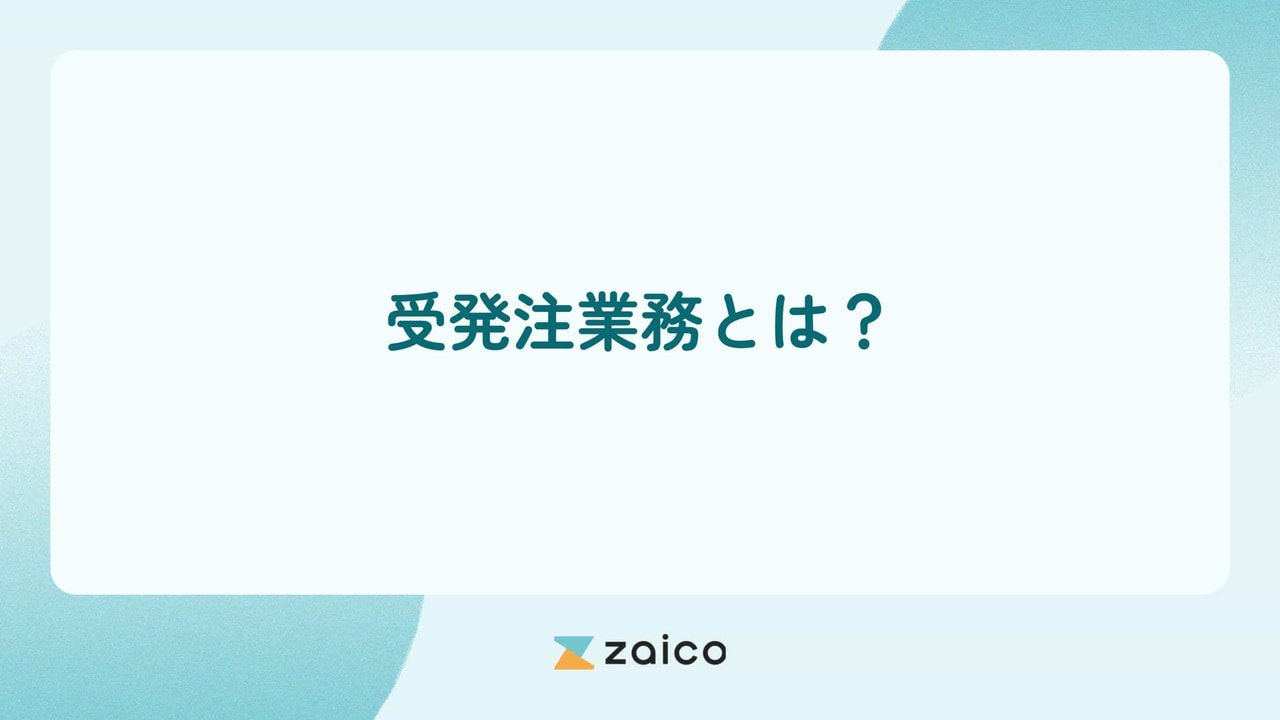FAXでの受注を続けている企業は少なくありません。
しかし、デジタル化の流れが加速し、FAX受注に限界を感じて「そろそろやめたい」と考えることもあるでしょう。
FAX受注を続けることで発生するリスクを理解し、改善に向けた方法を知ることは、自社の競争力を維持するために欠かせません。
FAX受注をやめたいと考える理由や改善方法とFAX受注をやめたいと考えてからの移行のステップについて解説します。
FAX受注をやめたい理由
FAX受注をやめたいと考える背景には、日常業務に潜む多くの非効率が隠れています。
受注処理の速度や正確性が求められる現代において、FAXというアナログ手段に依存していることは、企業の成長に大きな足かせとなりかねません。
FAX受注をやめたい理由を確認していきましょう。
手作業の入力が非効率だから
FAXで届いた注文内容を担当者が基幹システムやExcelに手入力するのは、大きな時間的コストを伴います。
注文数が増えるほど入力業務が膨大になり、担当者が残業を強いられるケースも少なくありません。
特に繁忙期には「注文処理に追われて顧客対応が後回しになる」といった悪循環が生まれます。
本来であれば付加価値を生む営業活動や提案に人材を割くべきところを、単純作業に労力を費やしてしまう点が大きな課題です。
読み取りミスや入力ミスが発生するから
FAX注文は手書きの文字やかすれた印字が多く、判読が難しいケースが頻発します。
担当者の読み間違いによる入力ミスや、数字の桁を誤って入力してしまうと、誤出荷や納品遅れといった重大なトラブルに直結します。
こうしたミスは1件あたりの対応コストだけでなく、顧客からの信頼低下にもつながるため、企業にとっては見えにくい大きな損失となります。
在庫反映が遅れ納期遅延を招くから
FAX注文はリアルタイムでシステムに反映されるわけではありません。
受注担当者が入力するまでの時間差によって、在庫状況が正確に把握できず、欠品や納期遅延を引き起こすリスクが高まります。
たとえば、複数の注文が同時にFAXで届いた場合、先に入力された注文に在庫が割り当てられ、後から処理された注文が欠品扱いになるケースもあります。
結果として「注文したのに納期通りに届かない」という不満が顧客に残り、クレーム対応に余計な工数がかかります。
注文内容の共有に時間がかかるから
FAXは紙媒体で届くため、営業部門や倉庫、経理部門など関係部署に情報を共有する際にコピーやスキャン、転送といった追加作業が必要です。
データが一元管理されていないことで、どの部署が最新情報を持っているのか不明確になりやすく、確認や承認フローの遅れが全体の業務効率を下げる要因となります。
「誰がどの注文を処理しているのか分からない」といった属人化の問題も深刻化します。
競合他社とのデジタル化格差が広がるから
現在、多くの企業がWeb受注やEDIなどの仕組みを導入し、リアルタイムで正確な受注処理を実現しています。
その一方でFAX受注を続ける企業は、取引スピードや処理精度で後れを取りやすくなります。
顧客にとっても「オンラインで即時注文できる企業」と「FAXで手間がかかる企業」を比較すれば、前者を選ぶのは自然な流れです。
結果的にビジネスチャンスを逃し、競合との差は年々拡大していくことになります。
FAX受注をやめたいのに続けるリスク
「やめたい」と思いながらFAX受注を続けることには、長期的に大きなリスクがあります。
単なる不便さにとどまらず、顧客対応の質や社内コスト、将来的な事業展開にまで悪影響を及ぼします。
FAX受注をやめたいのに続けるリスクを確認していきましょう。
顧客満足度の低下につながる
FAX受注はどうしても誤出荷や納期遅延を招きやすくなります。
顧客にとっては「約束通りに商品が届かない」「注文内容が正しく反映されていない」といった不満が積み重なります。
取引先は信頼できる他社へ流れてしまう可能性が高く、既存顧客を失うことは新規顧客の獲得以上に大きな損失となります。
内部コストの増加で利益を圧迫する
FAX受注には人件費・紙代・トナー・通信費など、目に見えにくいコストがかかっています。
たとえば、1件の注文入力に5分かかる場合、1日100件なら500分=8時間以上が入力作業に費やされます。
これは1人分の人件費に直結し、企業の利益率を確実に圧迫します。
業務効率が悪化するほど、利益の出にくい体質へと陥ってしまうのです。
属人化による業務停滞のリスクがある
FAX受注はマニュアル化が不十分な場合が多く、担当者の経験や判断に依存する傾向があります。
特定の社員だけが処理方法を知っていると、その人が休職・退職したときに業務が回らなくなります。
結果として顧客対応が遅れたり、代替人員の教育に時間とコストを要するなど、組織の柔軟性を奪うリスクがあります。
災害・障害時に受注が止まるリスクがある
FAXは停電や機器の故障、通信障害に弱い仕組みです。
災害時には通信環境が不安定になり、受注業務そのものが停止してしまう可能性があります。
システム化された仕組みであればクラウドからの復旧が可能ですが、FAX依存では復旧までに長時間を要し、その間に顧客の不満や機会損失が拡大します。
DX推進の妨げになる
現在、多くの企業がDXを進め、データ活用による生産性向上や新規ビジネスの創出に取り組んでいます。
ところがFAX受注はデータが紙で止まり、システムに蓄積・分析できません。
結果として、DXの基盤となるデータ活用が進まず、将来的に競合との差がますます広がる大きな足かせとなります。
FAX受注をやめたい時の改善方法
FAX受注の課題を解決するには、デジタル技術を活用した改善策が有効です。
アナログな受注体制を徐々に変えていくことで、現場の負担を軽減し、顧客満足度の高い仕組みへ移行できます。
FAX受注をやめたい時の改善方法を確認していきましょう。
受注内容をデジタル化して自動反映する
FAXでの受注を続ける最大の問題は「紙からデータへの変換」です。
これを最初からデジタルで入力してもらう仕組みに切り替えれば、手入力が不要になり、大幅な効率化が可能です。
たとえば、取引先に専用の注文フォームを提供すれば、入力内容がそのまま自社システムに反映されます。
結果として「入力作業ゼロ」「反映までのタイムラグなし」を実現でき、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。
OCRを活用してFAX注文を自動読み取りする
すぐにFAXを完全廃止できない企業も多いため、移行の中間ステップとして有効なのがOCR(光学文字認識)の活用です。
紙で届いたFAX注文書をスキャンすれば、自動で文字情報をデータ化し、そのまま基幹システムへ取り込むことができます。
人が文字を読み取って入力する必要がなくなり、誤入力防止と省力化が同時に可能になります。
特に取引先の事情でFAX注文が当面残る場合でも、業務効率化を一気に進められる現実的な方法です。
受注システムを導入する
FAXを根本的にやめるには、EDIやWeb受注システムの導入が最も効果的です。
EDI(電子データ交換)は大規模な取引に適しており、取引先との注文データを直接システム連携できます。
一方、中小規模の企業であれば、Web発注サイトや専用アプリを導入することで簡単にデジタル化が実現できます。
受注のスピードが飛躍的に向上することで、注文履歴の管理・分析も容易になるため、顧客対応や在庫計画の精度も高まるでしょう。
在庫管理システムと連携する
受注業務をデジタル化するだけでなく、在庫管理システムと連携させることが重要です。
受注データがリアルタイムに在庫と同期すれば、欠品や過剰在庫といったトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば「注文が入った瞬間に在庫が引き当てられる」「在庫不足の場合は自動でアラートが出る」といった仕組みを整えることで、納期遅延のリスクを減らし、顧客満足度を高められます。
さらに、受注と在庫のデータが統合されることで、将来的な需要予測や仕入れ計画の最適化にもつながるでしょう。
FAX受注をやめたい時の改善の流れ
FAX受注をやめたい場合、いきなり全てを切り替えるのではなく、段階的に移行することが成功のポイントです。
現場の混乱を防ぎ、スムーズに新しい仕組みを浸透させるためには、順を追った改善プロセスが欠かせません。
FAX受注をやめたい時の改善の流れを確認していきましょう。
現状の受注フローを可視化する
まずは、FAXで受け取った注文がどのように処理されているのかを整理します。
注文の受信から入力、在庫の確認、出荷指示までの流れを明文化し、実際に担当者へヒアリングすることで、業務の全体像を把握できます。
ここで「どこで時間がかかっているのか」「ミスが発生しやすい工程はどこか」を洗い出すことが、改善の第一歩となります。
改善すべき課題を洗い出す
次に、現状フローを基に具体的な課題を抽出します。
たとえば「入力に1件5分以上かかる」「在庫反映が遅れる」「社内共有に二重の手間がある」など、定量化できる課題をリスト化します。
その中から優先度の高いものを選び、改善計画を立てることが重要です。
自社に合った受注システムを選定する
課題が明確になったら、それを解決できる受注システムを検討します。
小規模企業であれば、Webフォームやクラウド受注アプリが導入しやすく、取引先も使いやすいのが特徴です。
大規模企業や取引先が多い場合には、EDI(電子データ交換)の導入が適しています。
自社の規模や取引特性に応じて、最適なシステムを選定することが成功のカギです。
テスト運用を行い社内に浸透させる
新しい仕組みは一気に切り替えるのではなく、まずは一部の部署や主要取引先との間でテスト運用を行います。
この段階で「入力ルールが守られているか」「在庫管理と連携できているか」などを確認し、問題点を洗い出して改善します。
並行して、従業員への教育やマニュアル整備を進めることで、社内全体へのスムーズな浸透が可能になります。
完全移行し継続的に改善する
テスト運用で得られた課題をクリアしたら、FAX受注を完全に廃止し、デジタル受注へ移行します。
移行後も定期的に運用を振り返り、業務フローの改善やシステムのアップデートを継続することが大切です。
こうすることで、一時的な効率化にとどまらず、長期的に競争力を高めることができます。
FAX受注をやめたいならzaico
FAX受注からの脱却を検討しているなら、在庫管理と受注業務を効率化できる「クラウド在庫管理システムzaico」の導入をご検討ください。
zaicoはクラウド型の在庫管理システムで、受注データをリアルタイムに反映し、在庫情報と自動連携することが可能です。
zaicoを導入することで、FAX受注にありがちな入力ミスや在庫の反映遅れといった課題を解消できます。
また、OCR機能やスマートフォン・タブレットからも利用できるため、現場担当者も直感的に操作でき、社内全体での定着が早い点も大きなメリットです。
FAX受注をやめたい、改善したいとお考えであればお気軽にzaicoにお問い合わせください。