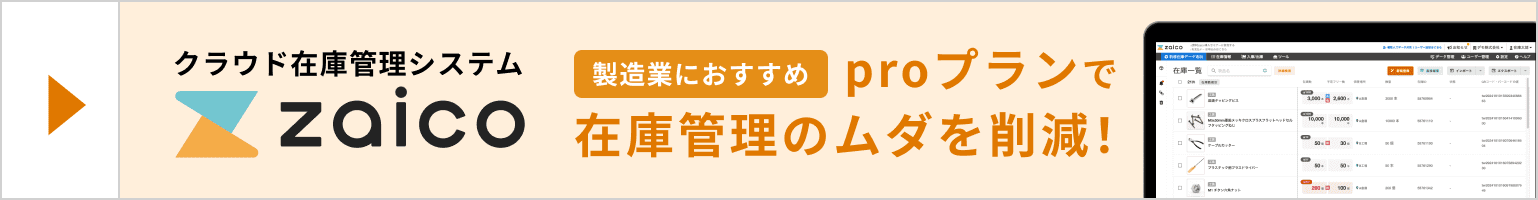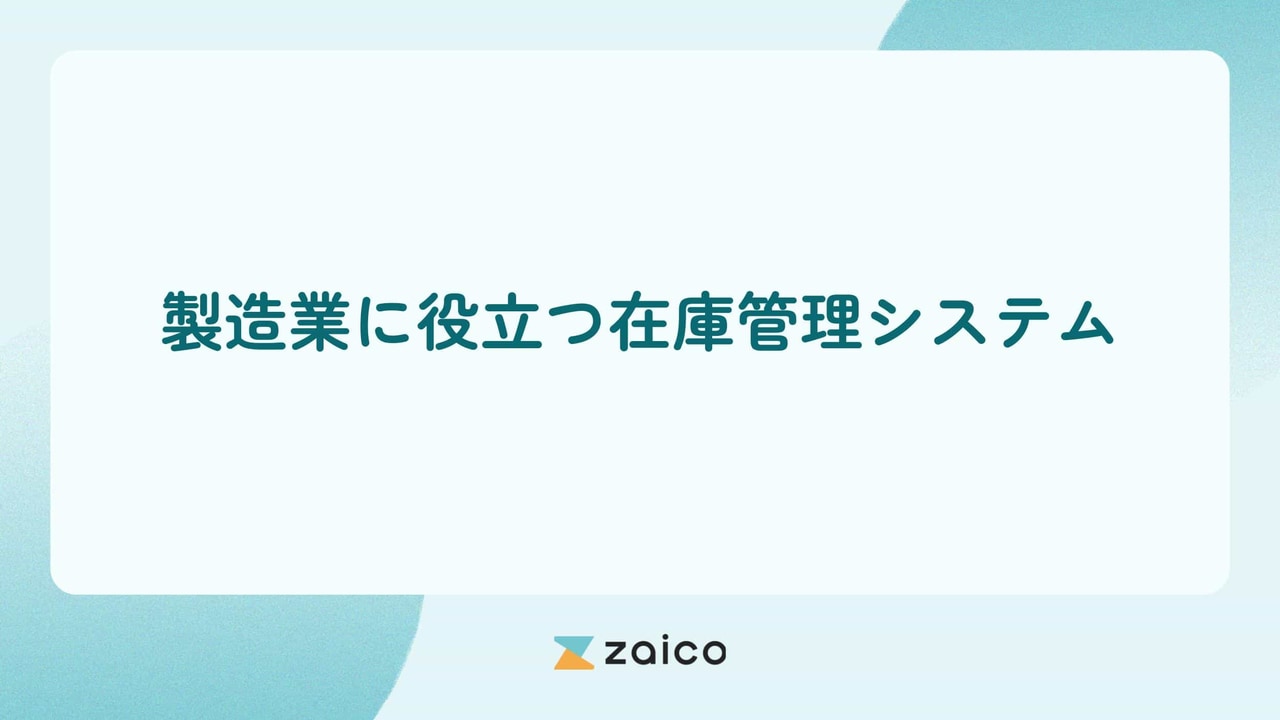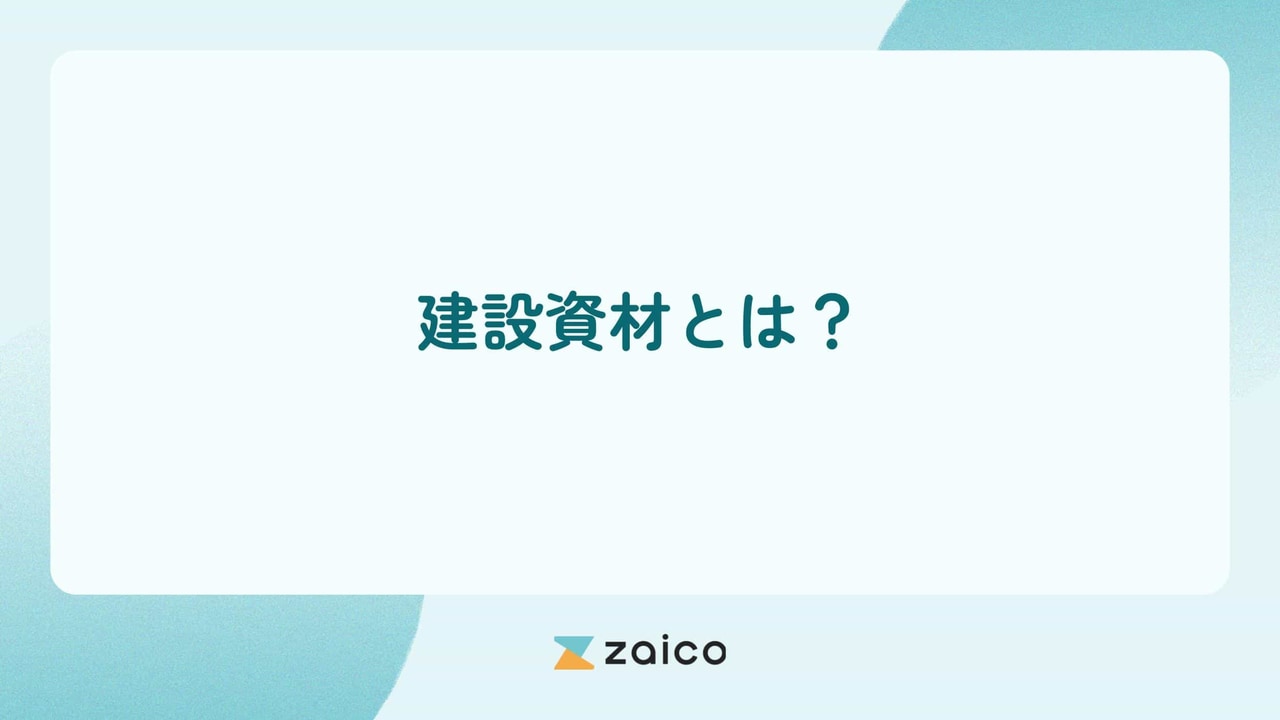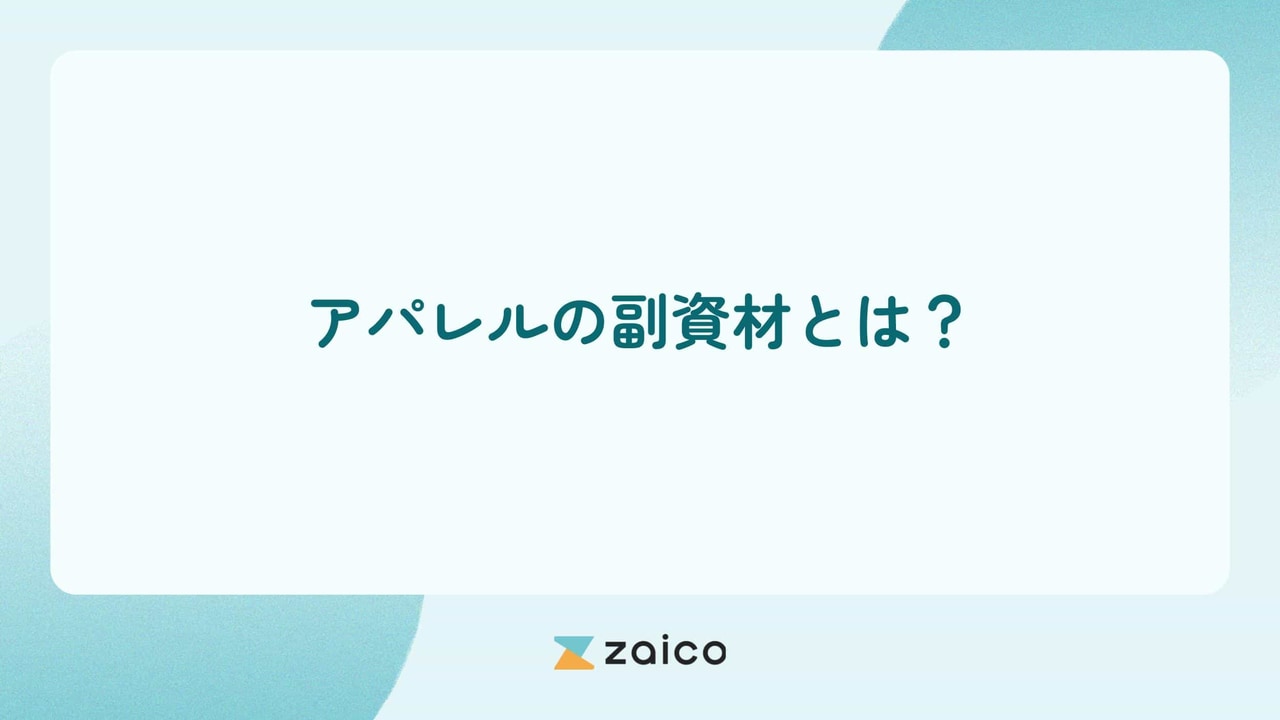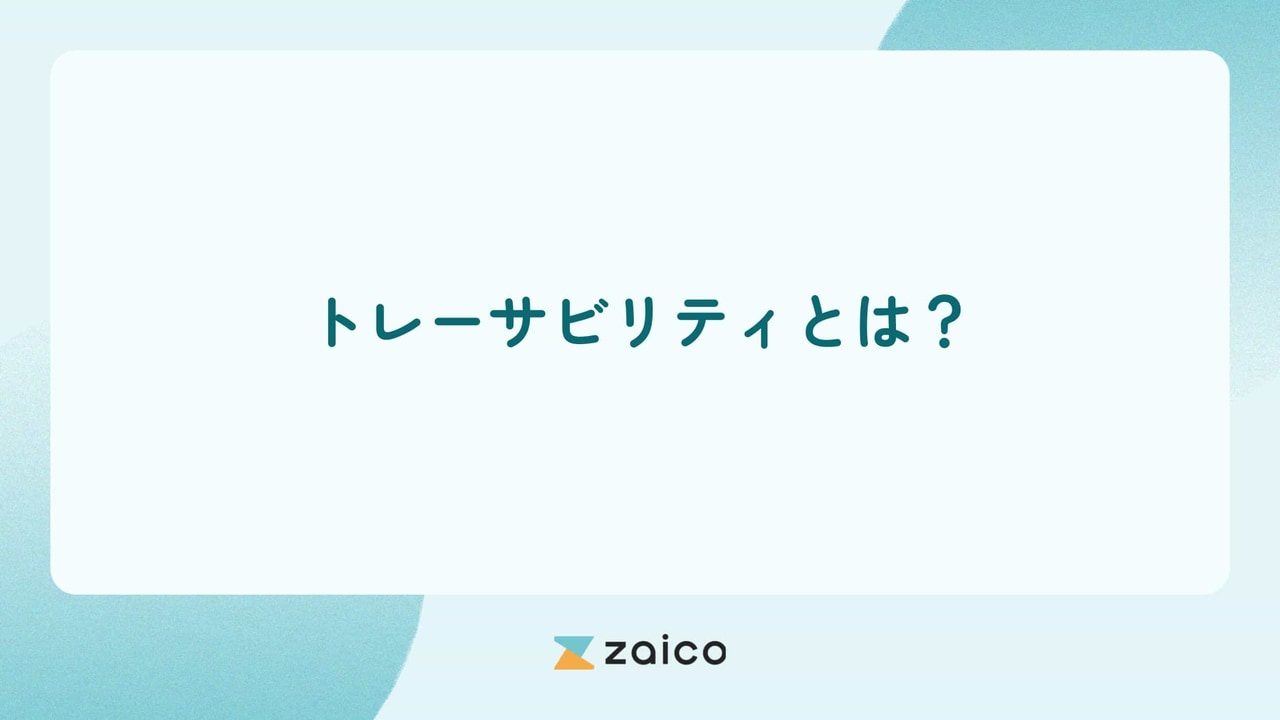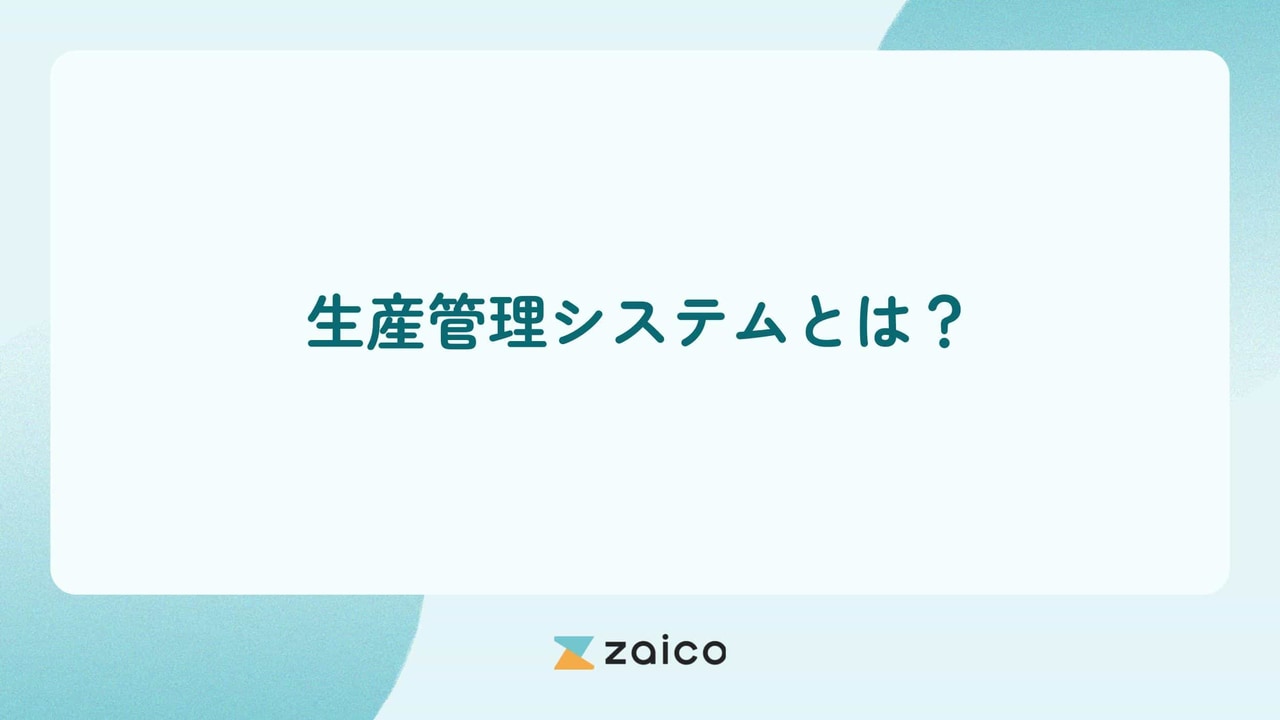製造業において、安定した製品供給とコスト効率の向上を実現するためには、精度の高い生産計画が不可欠であり、生産計画の立て方が重要になります。
適切な計画を立てることで、コスト削減と納期遵守を両立し、競争力のある製造体制を構築できます。
一方、市場環境の変化や現場の制約により、理想的な計画の実現には多くの課題があることも事実です。
生産計画の立て方から、よくある生産計画の立て方の失敗例、生産計画の立て方を改善するポイントを確認していきましょう。
生産計画の立て方を理解するための基礎知識
生産計画を効果的に立てるためには、基礎となる概念の理解が重要です。
生産計画の立て方の前に生産計画とは何か、どのような種類があるのかを確認していきましょう。
生産計画とは
生産計画とは、顧客の需要に応えるために「いつ、何を、どれだけ、どのように」生産するかを決定する計画のことです。
生産計画の主な目的は、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」のQCDを維持・向上させることにあります。
適切な生産計画を作成し実行できれば、顧客の需要を満たしながら、無駄なコストを削減し、スピーディーな納品と納期遵守を実現可能です。
生産計画の種類
生産計画は、その期間の長さによって大きく「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」の3つに分けられます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
大日程計画:3ヶ月から1年の長期的な視点で、生産量や生産能力の目標を設定する計画
中日程計画:1ヶ月から3ヶ月程度の期間で、大日程計画に基づき、製品ごとの生産量や納期を決定する計画
小日程計画:1週間から1ヶ月単位で、個々の作業や機械の稼働スケジュールなどを決定する計画
生産計画の立て方も計画の期間や内容に応じて考えていく必要があります。
生産計画の立て方
それでは、実際に生産計画をどのように立てていくのがいいのでしょうか。
それぞれの計画に応じた生産計画の立て方について確認していきましょう。
大日程計画の立て方
大日程計画は3ヶ月から1年間の長期的な生産活動の基本方針を決定する計画です。
企業の経営戦略に基づいて、将来的に必要となる生産量や資源を予測し、計画を策定します。
大日程計画では、過去の販売実績や市場トレンド、景気動向などを分析した需要予測が重要です。
需要予測に基づいて、年間の総生産量や主要製品の生産目標を設定します。
また、現在の生産能力(設備や人員)で目標達成が可能かどうかの評価も行い、必要であれば設備投資や人員増強の計画も検討します。
中日程計画の立て方
中日程計画は1ヶ月から3ヶ月を対象とした計画です。
大日程計画で定めた目標を達成するために、具体的な製品ごとの生産量や納期を詳細に計画します。
中日程計画では、資材の納期や在庫状況、生産ラインの稼働状況、人員の配置などを考慮し、無理のない計画を立てることが重要です。
特に、部品の調達リードタイム(発注から納入までの期間)は計画に大きな影響を与えるため、正確に把握しておく必要があります。
小日程計画の立て方
小日程計画は1週間から1ヶ月程度の短期的な日程計画です。
中日程計画に基づいて、どの製品を、いつ、どの生産ラインで、どの作業者が、どのくらいの時間で生産するのかといった日々の生産活動を決定します。
工程ごとの負荷情報を確認し、ラインバランスを調整したうえで、日々の生産進捗を実績と比較しながら計画を調整していきましょう。
機械の故障や人員の急な欠勤など、現場の状況に合わせて柔軟に対応できるよう、ある程度の余裕を持たせることも大切です。
生産計画の立て方:よくある失敗例
生産計画を苦労して立てても、さまざまな要因によって計画どおりに進まないことも少なくありません。
多くの企業が直面する失敗例の中から、生産計画の立て方でよくある失敗例について確認していきましょう。
誤った需要予測による生産計画の破綻
需要予測の精度が低いことは、生産計画の最も深刻な問題の1つです。
需要を過大に見積もると、過剰な在庫を抱え、保管コストや廃棄ロスの増加につながります。
逆に、需要を過小に見積もると、欠品が発生し、販売機会の損失や顧客満足度の低下を招く原因です。
このような問題を避けるためには、複数の予測手法の併用と定期的な見直しが必要です。
生産能力を無視した無理な計画立案
生産能力を無視した無理な計画立案は、よくある失敗例の1つです。
設備の能力を超えた生産計画は、品質低下や設備故障のリスクを高め、結果的に計画達成を困難にします。
また、人員不足や技能レベルを考慮せずに、売上目標や顧客要求だけを重視した計画を立ててしまうと、現場に過度な負担をかけることになります。
結果として、納期遅延や従業員の疲弊などの問題を引き起こし、長期的には企業の競争力低下を招く原因です。
現場とのコミュニケーション不足による計画と実態の乖離
計画部門が一方的に生産計画を策定し、現場の意見や状況を十分に吸い上げていない場合、計画と実際の作業状況に乖離が生じることがあります。
機械の調子、作業員の熟練度、作業手順の細かな問題点など現場でしか知り得ない情報が計画に反映されないと、計画は絵に描いた餅になりかねません。
現場との定期的な情報共有と意見交換が不可欠です。
納期を優先した計画の詰め込み過ぎ
顧客の納期要求に応えようとするあまり、無理なスケジュールを組んでしまうことも失敗の要因です。
計画を詰め込みすぎると、わずかなトラブルや遅延が全体の生産計画に大きな影響を与えてしまいます。
結果として、品質管理がおろそかになったり、作業員の長時間労働を招いたりして納期遅延を引き起こすという悪循環に陥るリスクが高まるでしょう。
適切な優先順位付けと現実的なスケジューリングが重要です。
生産計画の立て方を改善するポイント
効果的な生産計画を立案するためには、改善ポイントを理解し、継続的に取り組むことが重要です。
生産計画の立て方を改善するためのポイントを解説します。
需要予測の精度向上と定期的な見直し
効果的な生産計画を立てるには、需要予測の精度向上が欠かせません。
需要予測の精度向上には過去データの分析だけでなく、市場トレンドや競合の動向、経済指標など、さまざまな情報を多角的に収集・分析することが重要です。
しかし、予測はあくまで予測であり常に変動する可能性があるため、定期的に見直しを行い、必要に応じて生産計画を柔軟に修正していくことで現状との隔たりを小さくできます。
現場との連携強化と情報共有の仕組みづくり
生産計画を実効性のあるものにするには、計画部門と生産現場の連携が重要です。
定期的な会議やコミュニケーションの機会を設け、現場からのフィードバックを計画に反映させる仕組みを構築しましょう。
現場で収集した情報をもとに生産計画を作成し、作成した計画にしたがって現場で作業するというサイクルを確立することで、計画と実態の乖離を最小限に抑えられます。
生産能力・リソース管理の徹底
無理のない計画を立てるためには、自社の生産能力や設備・人員・原材料などのリソースの正確な把握が不可欠です。
設備の稼働状況やメンテナンス履歴、作業員のスキルマップ、原材料の在庫状況などを常に最新の状態に保ちましょう。
正確な生産能力やリソースを計画に反映させることで、ボトルネックの発生を防ぎ、生産効率を最大化できます。
適度なバッファ(余裕)の設定
予期せぬトラブルや緊急の注文に対応できるよう、生産計画には適度なバッファ(余裕)を設けることも重要です。
例えば、生産ラインの稼働時間に少し余裕を持たせる、特定の部品の在庫を多めに持つなどの対策が考えられます。
ただし、過度なバッファは効率性を損なうため、過去のデータなどを参考に適正なバッファ量の見極めが必要です。
生産計画の立て方を理解して製造を効率化
適切な生産計画は、製造業における競争力の源泉です。
需要予測の精度向上や現場との連携、適切なバッファの設定により、環境変化にも柔軟に対応できる生産計画を立案できます。
作成した生産計画に基づいて、効率的な在庫管理を実施するなら「クラウド在庫管理システムzaico」をご検討ください。
zaicoで原材料から完成品まで一元管理することで、生産計画に沿った在庫管理を実現します。
生産計画の立て方に在庫管理部分の改善をお考えであれば、まずはお気軽にzaicoにご相談ください。