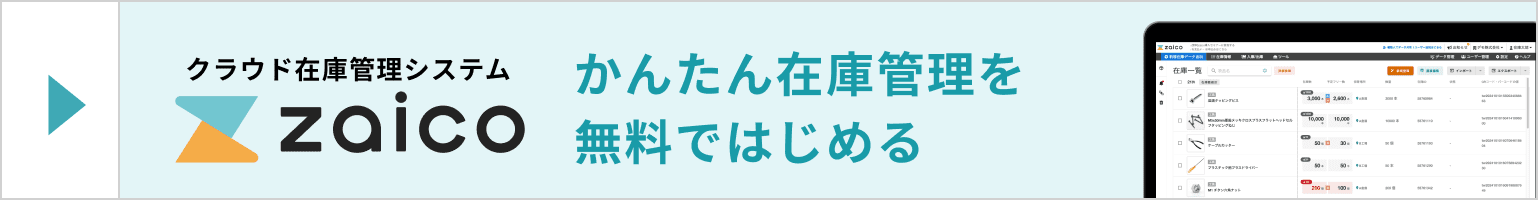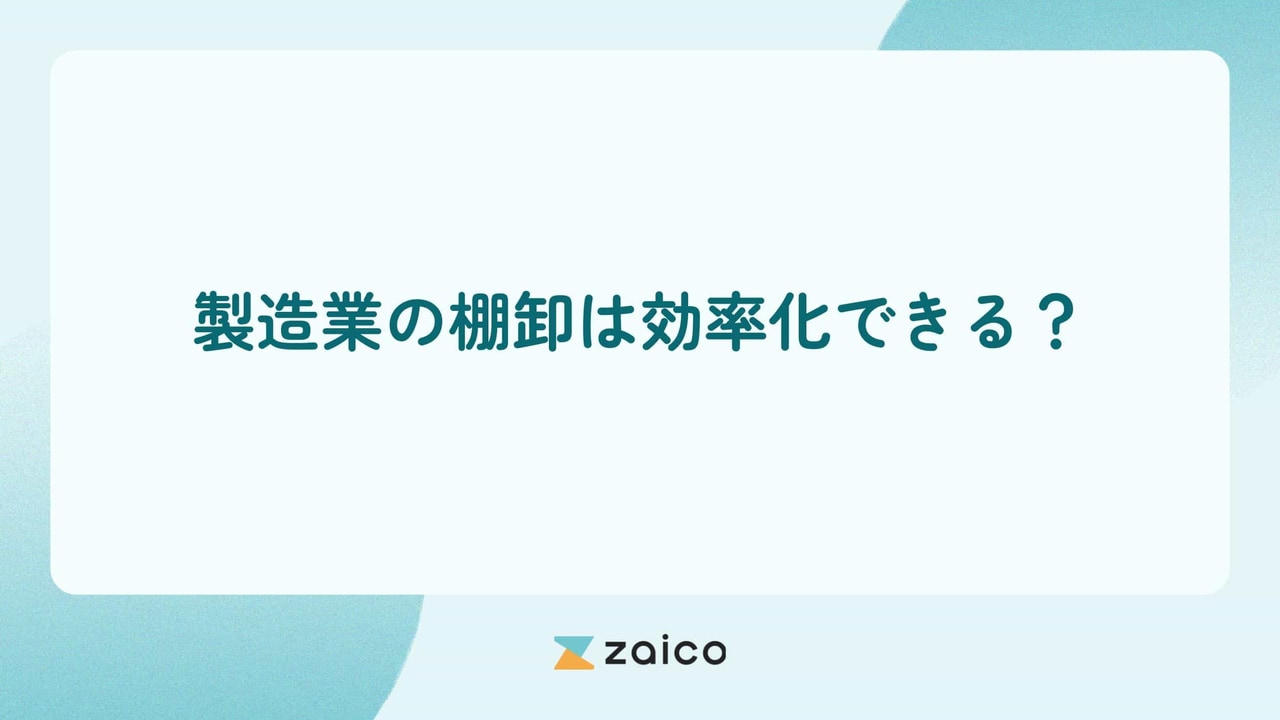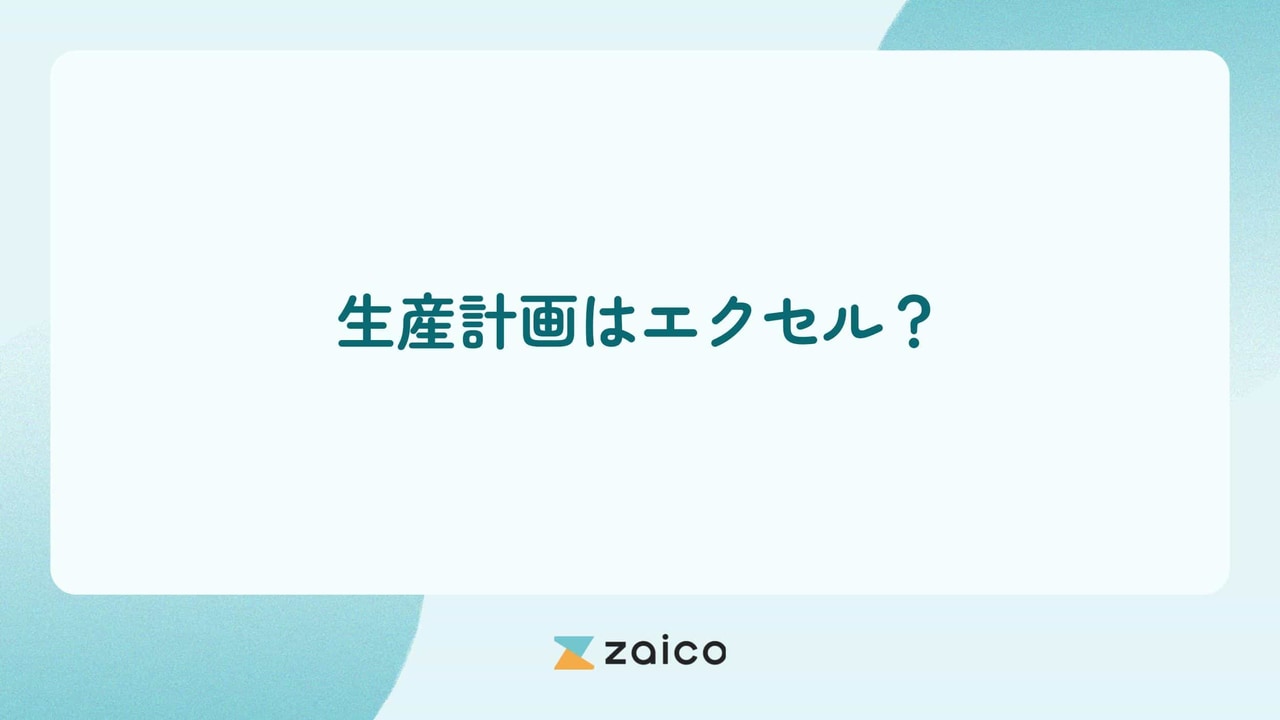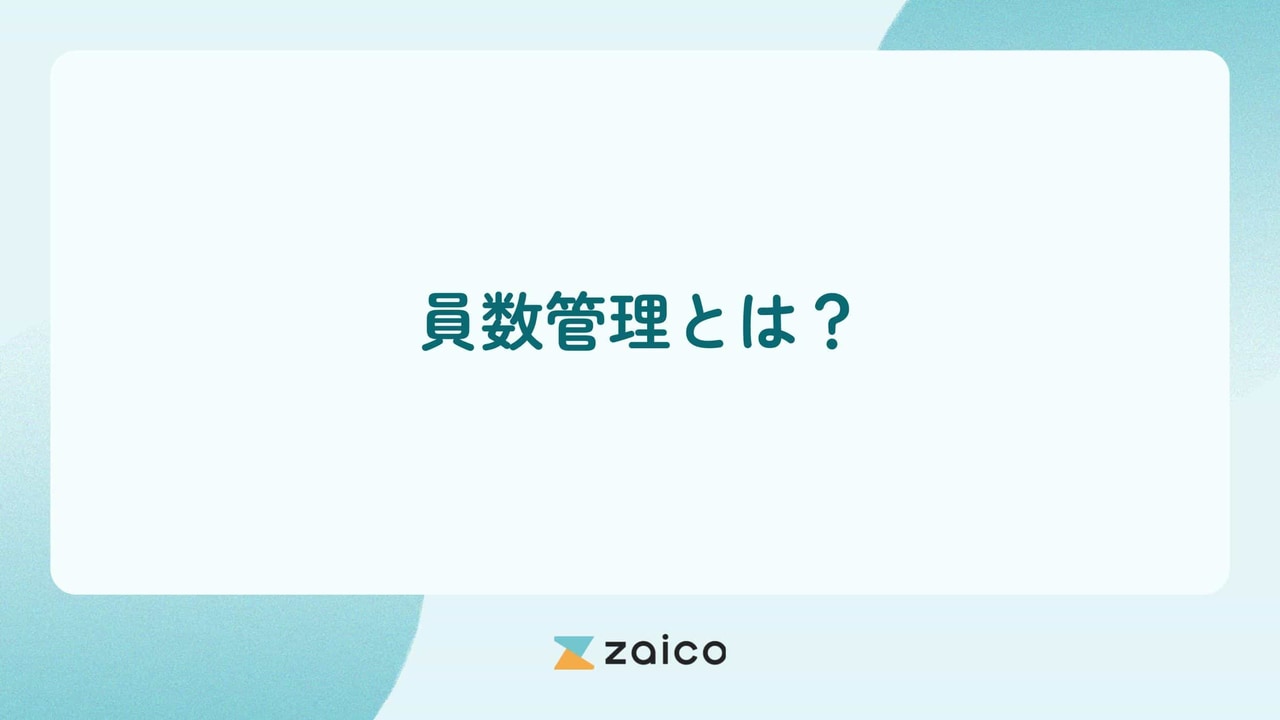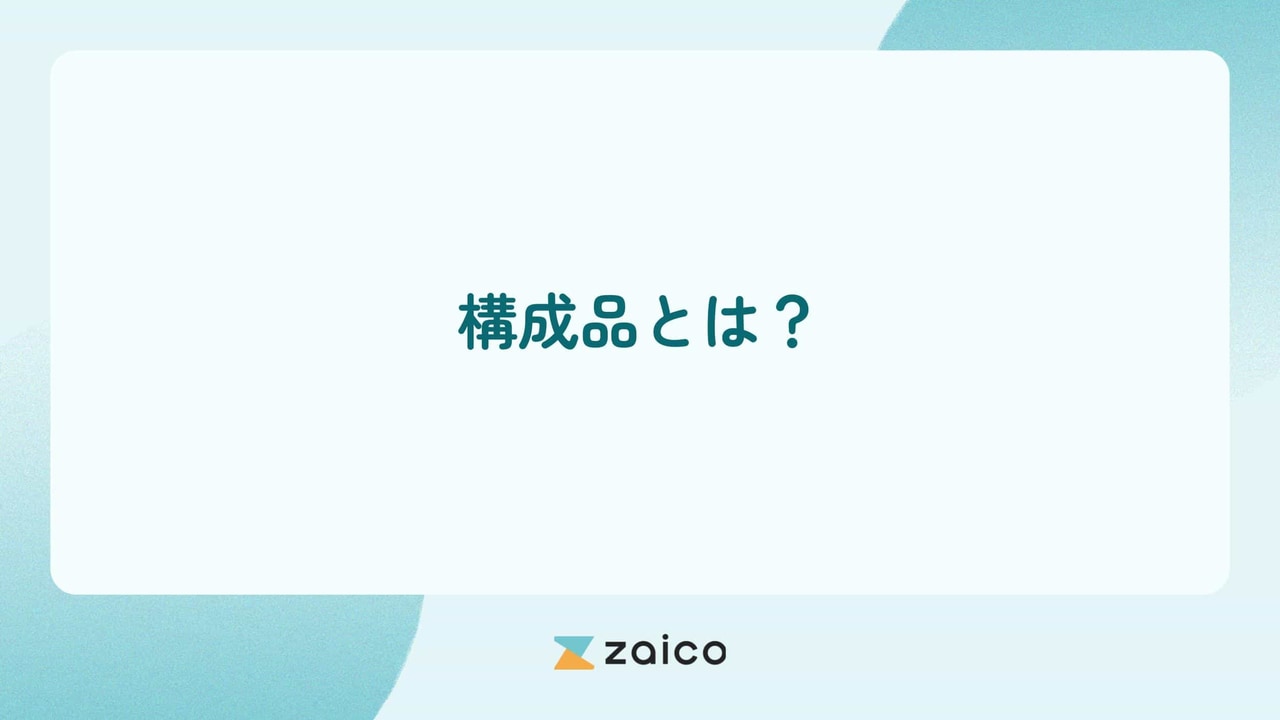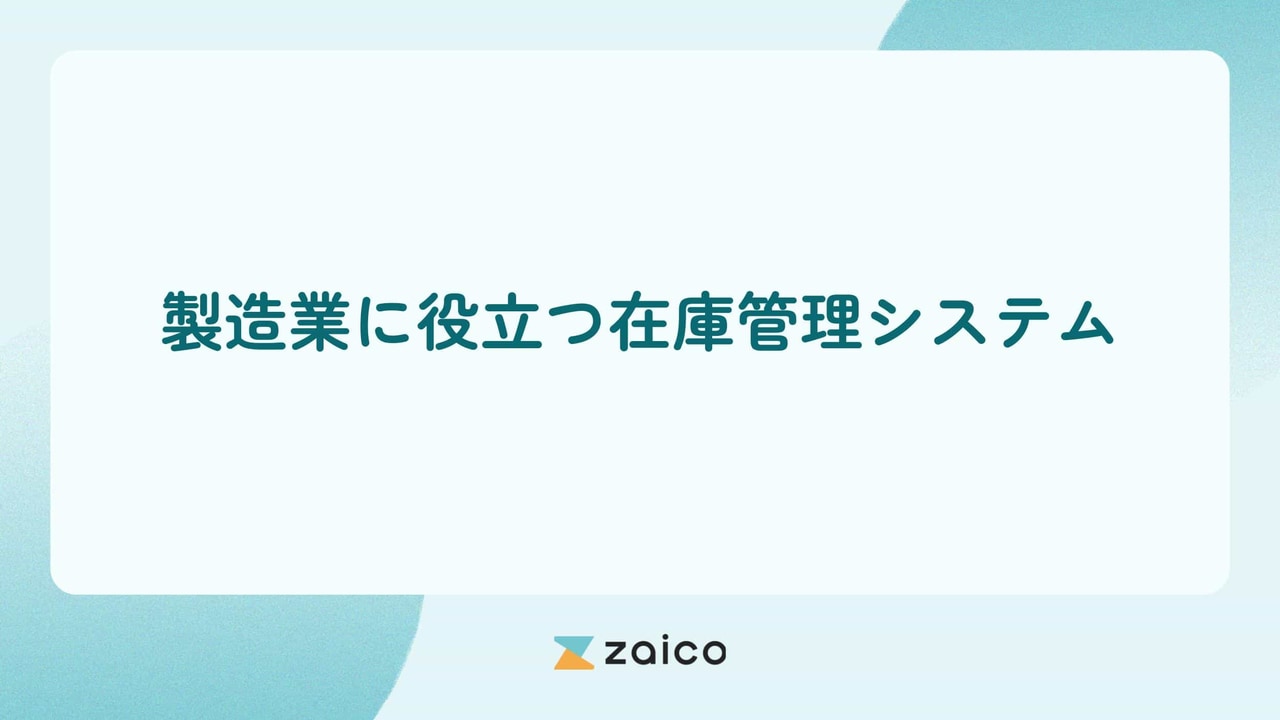製造業のDX事例には、人手不足や技術の属人化、業務の非効率といった課題を乗り越えるためのヒントが詰まっています。
現場に合った工夫やクラウドツールの導入により、コスト削減や品質の安定、業務の標準化を実現した企業も少なくありません。
製造業DX事例から学べるポイントとあわせて、現場の声が反映されなかったことでうまくいかなかった失敗事例なども交えて、製造業DX事例について確認していきましょう。
製造業のDX事例から考える必要性
製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務や仕組みを抜本的に見直し、生産性の向上やコスト削減、品質の安定などを実現する取り組みです。
紙の作業日報や目視による点検、ベテランの勘に頼った判断など、従来のやり方に限界を感じている企業も多いのではないでしょうか。
製造業DX事例が多くあることから、製造業DXが必要とされる背景を確認していきましょう。
人手不足と熟練工の高齢化への対応
製造現場では、少子高齢化の影響で若手人材の確保が難しくなり、同時に熟練工が定年を迎えるケースも増えています。
たとえば、機械のメンテナンスや製品の不良判定をベテランが目視で判断していた場合、その経験が退職とともに失われる恐れがあるでしょう。
こうした属人化を防ぐために、作業手順を動画や写真付きのマニュアルとしてデジタル化したり、設備の稼働状況をセンサーで記録して見える化したりする取り組みが有効です。
業務効率化とコスト削減の両立
手書きの日報、口頭での引き継ぎ、紙での在庫チェックなど、現場の業務には非効率な作業がいくつも残っている場合があります。
具体的には、出荷前検品の記録を紙で行っていると、ミスや記入漏れが起きやすく、確認にも時間がかかるでしょう。
方法をタブレット入力に変更するだけで、作業時間の短縮やデータの自動集計が可能になり、人的コストの削減にもつながります。
品質の安定化とトレーサビリティの確保
不良品の発生やクレーム対応の際に、どの工程で何が起きたかを正確に把握できるトレーサビリティの確保は、信頼を保つうえで欠かせません。
部品のロット番号や検査結果を紙で記録していると、探すのに時間がかかり、記録漏れのリスクも高まります。
製造実績や検査データをシステムで一元管理することで、「いつ」「誰が」「どんな状態で」製造したかをすぐに確認でき、スムーズに対応できるでしょう。
環境対応・サステナビリティの実現
工場で使用する電力や水の量、廃棄物の種類と量は環境に大きな影響を与えます。
たとえば、エネルギー使用量を設備ごとに把握できていなければ、無駄な稼働に気づけません。
エネルギー監視システムやCO2排出量の自動計測ツールを導入することで、改善ポイントが明確になり、脱炭素の推進や省エネにつながります。
こうした取り組みは、製造業のサステナビリティ実現に向けて重要な役割を果たすでしょう。
競争力強化と新たな付加価値創出
顧客のニーズが多様化し、製品にスピードやカスタマイズ性が求められる中、情報の把握と意思決定の速さが重要になっています。
製品別の生産進捗や在庫状況をリアルタイムで把握できれば、納期遅れのリスクを減らし、必要なタイミングで増産や調整が可能になります。
IoTやクラウドを活用した仕組みを取り入れることで、現場の見える化が進み、より柔軟で競争力のある製造体制を構築できるでしょう。
製造業DX事例:成功した事例
製造業におけるDXは、多くの企業で業務効率化や品質向上、コスト削減を実現しています。
実際に成果をあげた代表的な製造業DXの成功事例を確認していきましょう。
工場稼働を見える化した製造業の事例
工場内の設備や生産ラインの稼働状況をリアルタイムで把握するため、センサーやIoT機器を活用して、稼働率や停止時間、異常発生を可視化する取り組みが進んでいます。
なお、自動車部品を製造する企業では、各工程に設置したセンサーから収集したデータをクラウド上で分析し、生産状況を即座に把握できる仕組みを構築しました。
この取り組みにより、設備異常の早期発見と迅速な対応が可能となり、稼働率の向上や生産計画の精度改善につながったという報告があります。
さらに、蓄積した稼働データを活用し、保全スケジュールの最適化を実現し、計画外の停止やメンテナンスにかかるコストの削減効果もありました。
画像認識で検査を自動化した事例
製品の外観検査に画像認識技術を導入し、検査作業を自動化した電子部品メーカーでは、AIがカメラで撮影した製品の画像を解析し、微細なキズや汚れを高精度で検出しました。
従来の目視検査で起きていた検査のばらつきを解消し、不良品の流出を減らすことに成功したのです。
さらに、検査時間の短縮や検査員の負担軽減にもつながっています。
事務効率を高めた事例
発注書や納品書などの書類作成や管理に多くの時間と手間を取られていた企業では、紙ベースの書類が多く、情報の検索や共有にも時間がかかっていたため、業務全体の効率が低下していました。
そこで、クラウド型の業務管理システムを導入し、書類の電子化とワークフローの自動化に着手しました。
結果的に発注や承認のプロセスをオンラインで完結できるようになり、書類の検索や共有がスムーズになったのです。
事務作業にかかる時間が大幅に減り、担当者の負担軽減にもつながっています。
設計・製造を一元管理した事例
ある製造業の企業では、設計データと製造工程の情報が別々のシステムで管理されており、情報の共有や連携に時間と手間がかかっていました。
そこで、クラウドベースのPLM(製品ライフサイクル管理)システムを導入し、設計から製造までの情報を一元的に管理できる体制を整えました。
このシステムにより、設計変更の情報がリアルタイムで製造現場に伝わるようになり、ミスや手戻りの減少につながりました。
また、工程の進捗状況も一目で把握できるようになり、生産計画の調整がスムーズになったため、納期遅延のリスクを低減できました。
基幹システムと併用した事例
ERP(統合基幹業務システム)を導入し、各システムを一元管理する仕組みを構築している場合であっても、基幹システムを利用するまでもないものや、別で管理したい物品や備品等が出てくる場合もあります。
そのような場合に、在庫管理だけを別のシステムで運用するようにしたり、特定の物品や部署だけは基幹システムではないシステムを利用するということで効率化する事例もあります。
製造業DX事例:失敗した事例
製造業におけるDXは、多くの成功例がある一方で、現場の理解不足や人材不足、システムの不整合などによって失敗に終わるケースも少なくありません。
具体的に失敗した製造業DXの事例を確認していきましょう。
現場の理解不足で失敗した事例
現場スタッフのDXに対する理解や納得感が不足していたため、導入されたシステムが活用されずに失敗したケースがあります。
たとえば、現場の業務フローや実態を十分に把握せずにシステム設計を進めた結果、実務に合わない機能ばかりで使いにくさが目立ちました。
現場の声を取り入れないまま導入が強行されると、スタッフの抵抗感が強まり、結果的にDXプロジェクトが頓挫してしまいます。
IT人材不足により頓挫した事例
DX推進のための専門的なIT人材の担当者がいないことで、計画が途中で停滞した事例もありました。
システムの選定や導入、運用保守に必要なスキルやノウハウが不足していると、問題発生時の対応が遅れ、トラブルが長期化しやすくなります。
外部パートナーの活用や人材育成計画がないまま進めると、結果として計画倒れに終わってしまうことも多いでしょう。
レガシーシステムとの不整合があった事例
既存のレガシーシステムとの連携がうまくいかず、データの統合や連携が困難になったケースもあります。
新システムは古いシステムと互換性がなく、二重入力やデータの不整合が多発し、かえって業務が煩雑化しました。
こうしたトラブルは、事前の現状調査や検証不足が原因で、システム間の調整や段階的な切り替えが重要になります。
コストとROIが合わなかった事例
初期投資や運用コストに比べて、導入後の効果や投資回収(ROI)が期待を下回った企業も見られます。
過剰な機能を盛り込み、無理な短期間での効果実現を目指した結果、コストばかりが膨らみ導入継続が難しくなりました。
投資対効果のシミュレーションや段階的な導入で、少しずつ成功体験を積み上げることが重要です。
トップダウン導入で現場が使わなかった事例
経営層の判断だけでDXを導入したものの、現場スタッフの理解や協力を得られず、使われないまま失敗した事例もあります。
トップダウンで進める際には、現場の声を反映した説明や教育、使いやすさの工夫が欠かせません。
現場の抵抗を減らし、自発的な利用を促進する取り組みがDX成功の鍵となります。
製造業DX事例の成功例から学ぶべきポイント
製造業DXを成功するためには、いずれも共通して見られる工夫や考え方があります。
成功した製造業DXの事例から成功に導くための実践的なポイントを確認していきましょう。
スモールスタートで成功体験をつくる
最初から大規模なDXを実施すると、現場の混乱やコスト負担が大きくなりやすく、途中で頓挫するリスクもあります。
たとえば、生産計画の一部をデジタル化や特定ラインの稼働状況を見える化するなど、少しずつできることから着手すると、導入への抵抗感を抑えることができるでしょう。
成功体験を現場と共有し、社内の理解が深まるように工夫することが大切です。
現場とIT部門の連携を強化する
IT部門側が操作性や導線を十分に現場とすり合わせないままシステムを構築すると、「実際には使いづらい」と現場で敬遠されることもあるでしょう。
日常的に現場の声を聞きながら、業務の流れを理解したうえで設計や運用を進めることで、より定着しやすくなります。
必要であれば、定期的な意見交換の場を設けて、相互理解を深めることも効果的です。
外部パートナーの支援を活用する
自社だけでDXを進めようとすると、知見や技術の不足が障壁になることがあります。
IoTやAIなどの導入にあたって、社内に専門知識がないまま試行錯誤を続けても、時間とコストだけがかかって成果が出にくくなる恐れもあるでしょう。
こうした場面では、DXの実績をもつ外部のコンサルタントなどにサポートを受けることで、プロジェクトをスムーズに進めやすくなります。
必要な部分だけに限定して協力を仰ぐこともできるため、自社に合った方法を選びましょう。
データを活かした改善サイクルの構築する
単にシステムを導入するだけでは、DXの効果は持続しません。
蓄積されたデータをどう活用していくかが、次の成果につながる鍵になるでしょう。
設備の稼働データや不良発生率などを定期的に確認し、課題の傾向をつかむことで、早期の改善アクションにつなげることができます。
現場ごとに異なる特性を数値で把握することで、属人化を減らしながら継続的な改善が可能となります。
PDCAをデジタルで回せるような仕組みづくりが、DXの定着に役立つでしょう。
製造業のDX事例にも含まれるzaico
製造業のDX推進において、部品や資材の在庫管理は重要なポイントとなります。
正確な在庫管理ができなければ、生産遅延やコスト増加のリスクが高まるため、効率的な管理体制が求められています。
製造業のDX事例としても利用が広がっているのが、「クラウド在庫管理システムzaico」です。
zaicoは、スマホやタブレットからでも簡単に操作でき、バーコードやQRコードを使ったミスの少ない管理が可能です。
また、リアルタイムでのデータ共有ができるため、生産計画の精度向上や無駄な在庫削減に役立つでしょう。
実際にzaicoを導入し、さまざまな媒体で部品や資材の管理を効率化している事例も多数あります。
製造業において在庫管理の部分からDXを進めたいとお考えであれば、お気軽にzaicoにお問い合わせください。