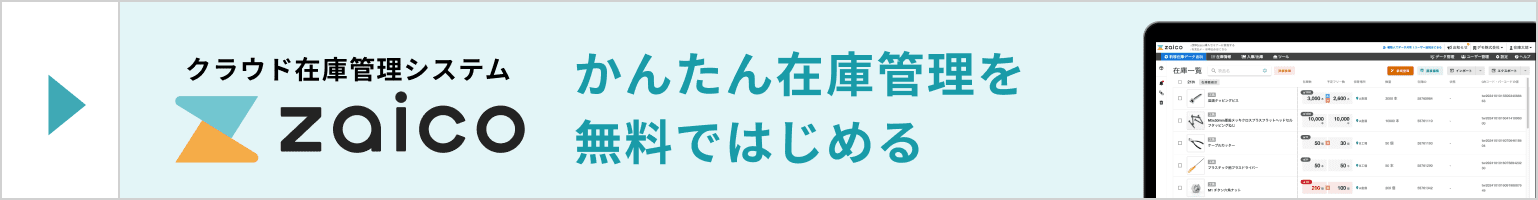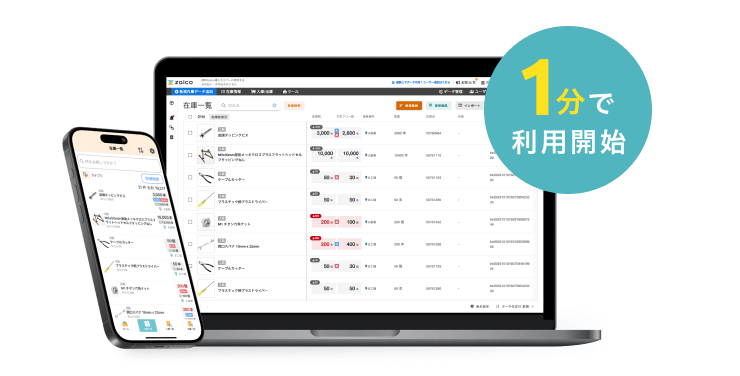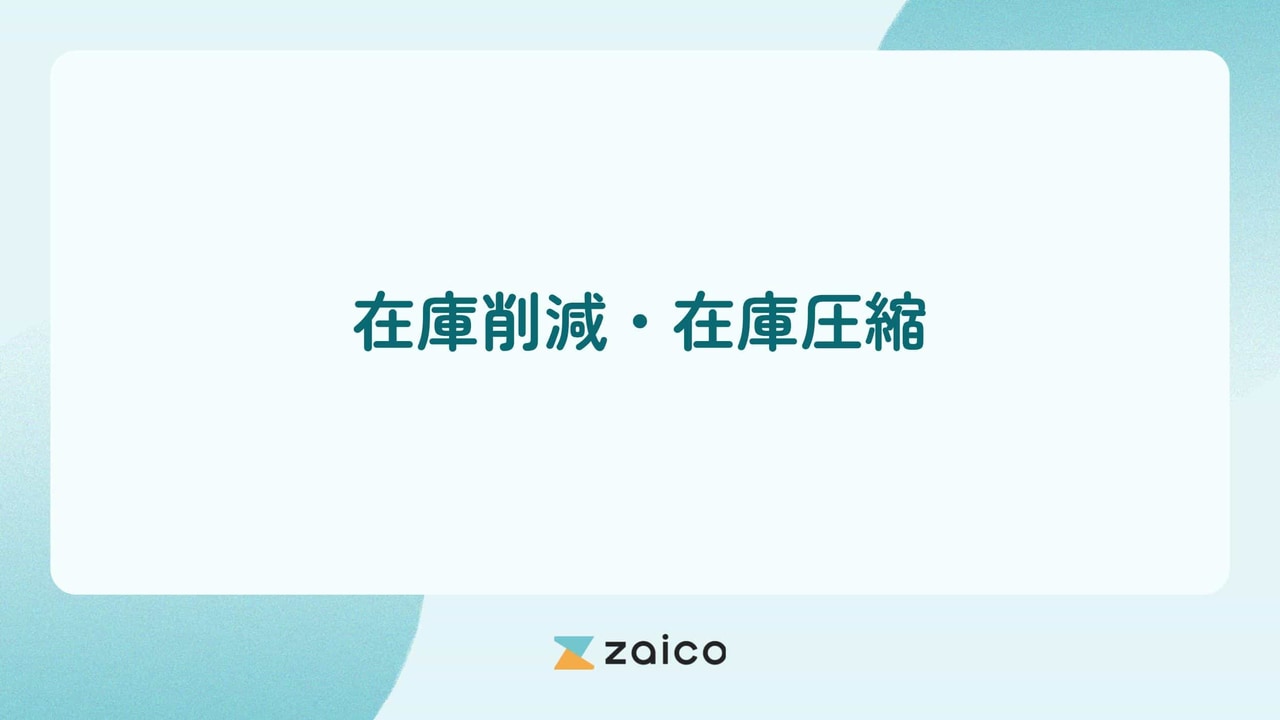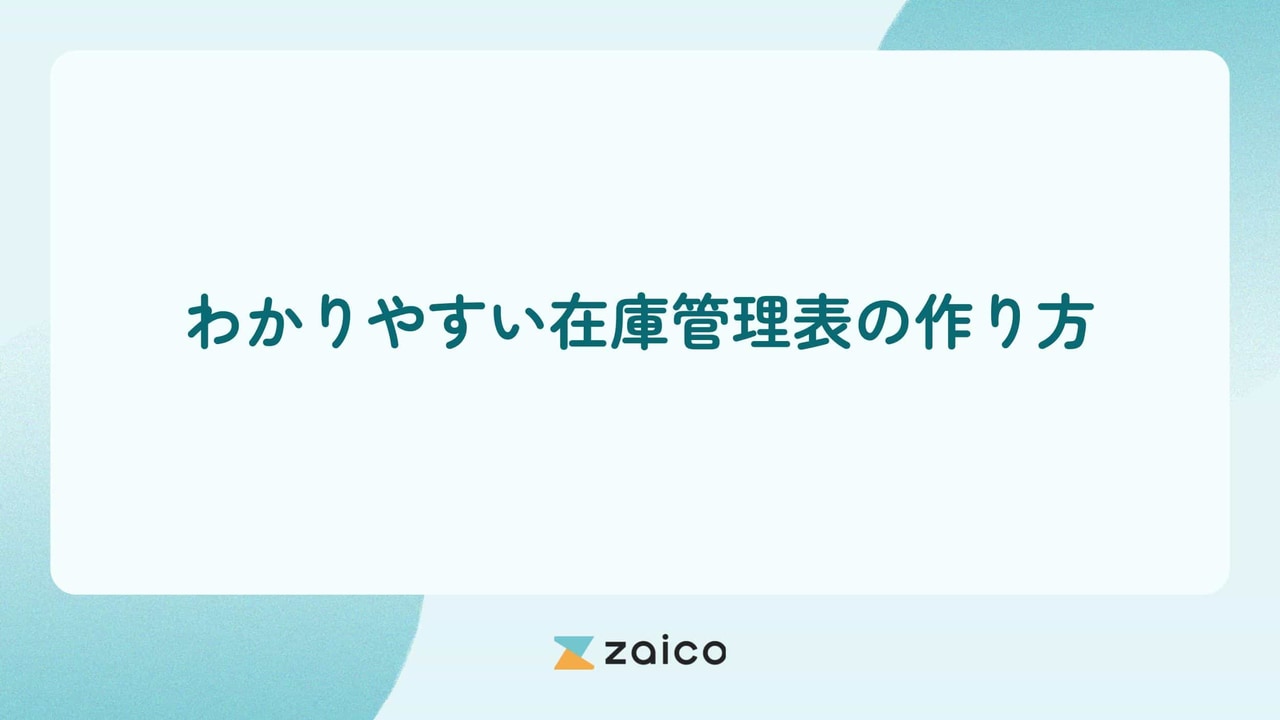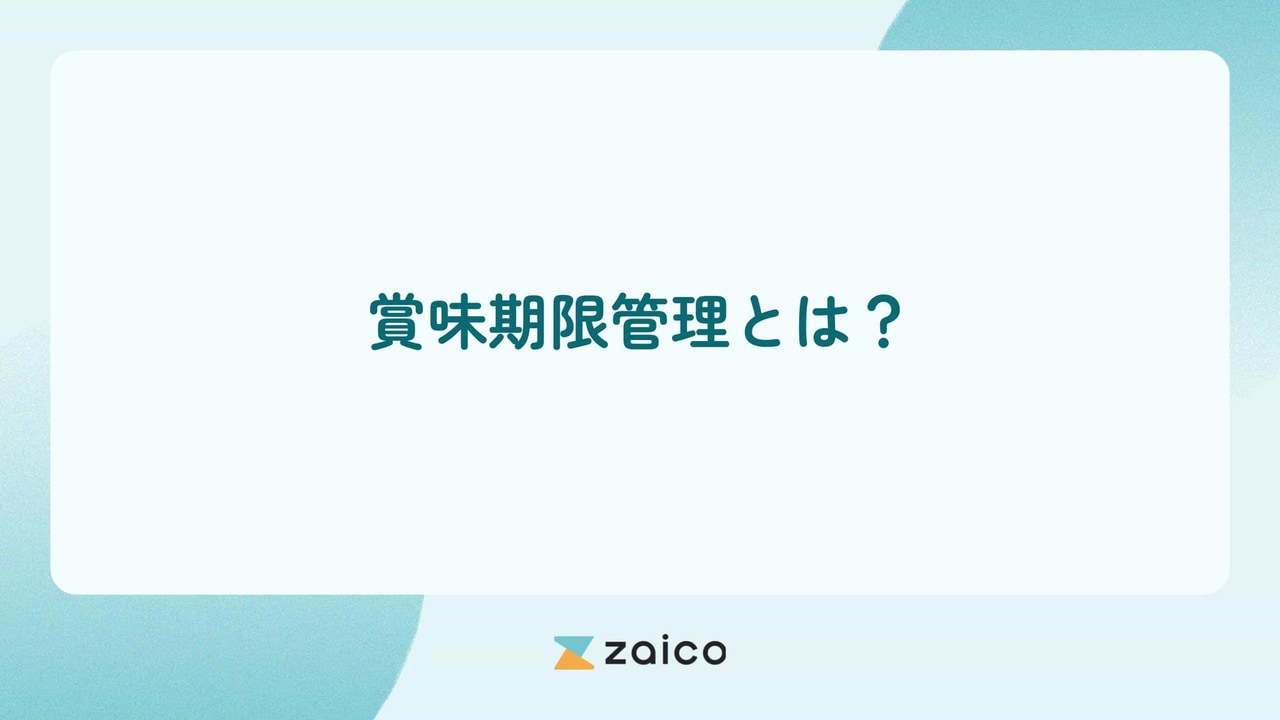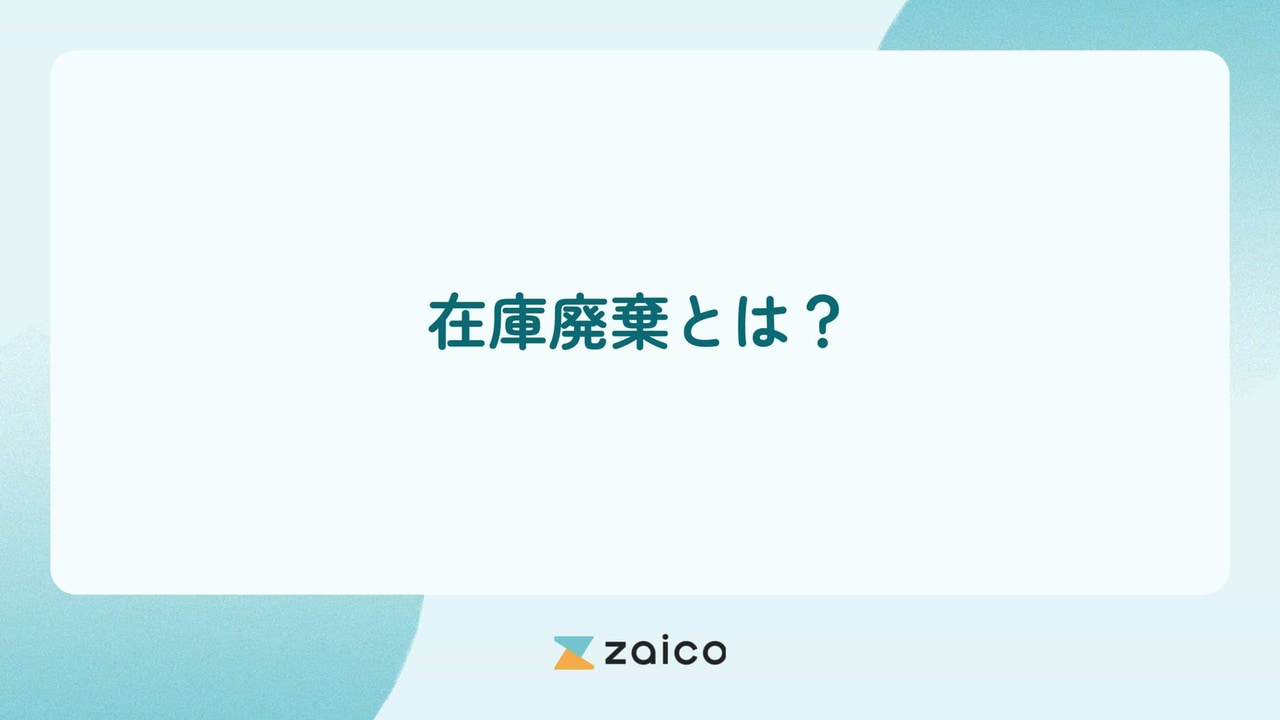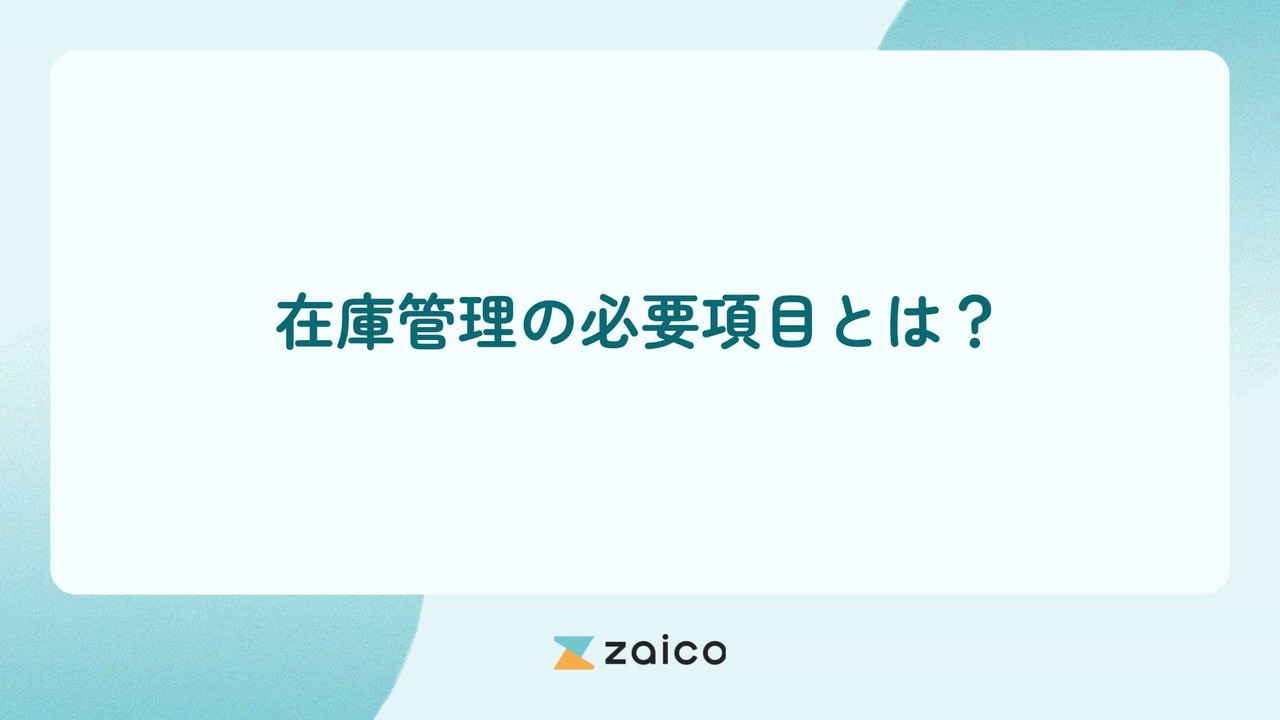在庫管理を行ううえで、在庫が適正かどうかを判断するための指標はいくつかあります。
その中でも特に重要なのが在庫月数です。
在庫月数を把握することで、今ある在庫が何か月分の販売量に相当するのかを定量的に把握できます。
過剰在庫や欠品を防ぎ、資金繰りや販売計画を安定させるためにも欠かせない考え方です。
在庫月数の基本的な意味から在庫月数の求め方、在庫月数を経営に役立てる活用方法を詳しく解説します。
在庫月数とは
在庫月数とは、現在保有している在庫が、平均的な販売ペースで何か月分に相当するかを示す指標です。
たとえば、月に100個売れている商品の在庫が300個あれば、その在庫月数は3か月分となります。
つまり、今の在庫で3か月間は販売を継続できるという意味です。
在庫月数の基本的な計算式は「在庫月数 = 現在の在庫数 ÷ 1か月あたりの平均販売数 」です。
この数値を把握することで、在庫を持ちすぎていないか、販売ペースに対して在庫が足りているかを判断できます。
業種や商材によって適正な在庫月数は異なりますが、一般的には1〜2か月分が目安とされています。
在庫月数とは:在庫月数が高すぎる場合のデメリット
在庫月数が高いということは、販売ペースに対して在庫を過剰に抱えている状態を意味します。
在庫月数が高すぎることで起こる主なデメリットを解説します。
資金繰りを圧迫する
過剰な在庫を抱えると、それだけ多くの資金が在庫として滞留します。
仕入れや製造にかかったコストが回収されずに倉庫内で眠っている状態となり、現金の流動性が低下します。
特に中小企業では、資金繰りの悪化が直接経営リスクにつながることも少なくありません。
必要以上に在庫を抱えることで、新しい商品の仕入れや投資、広告活動などの資金が回らなくなり、企業全体のキャッシュフローが停滞してしまう恐れがあります。
保管コストの増加
在庫を多く抱えれば抱えるほど、倉庫スペースの確保や管理にかかるコストが増加します。
倉庫の賃料や光熱費、人件費、さらには在庫の出し入れにかかる作業時間など、保管コストは目に見えにくい固定費として企業の利益を圧迫します。
また、在庫量が多いと商品ごとのロケーション管理の複雑さも増し、ピッキングミスや在庫差異の発生率も上がります。
これらの管理負担も、結果的に人件費や時間コストの増加につながります。
陳腐化・廃棄リスクの上昇
在庫月数が高い状態を放置すると、在庫の劣化や陳腐化が進み、販売できなくなるリスクが高まります。
特に、流行に左右される商品や賞味期限・使用期限のある商材では、長期保管によって価値が低下し、最悪の場合は廃棄せざるを得ません。
陳腐化在庫は、スペースの占有だけでなく損失計上の対象にもなるため、企業の財務健全性を損なう要因となります。
在庫月数とは:在庫月数が低すぎる場合のデメリット
在庫月数が低いということは、販売ペースに対して在庫量が少ない状態を指します。
在庫月数が低すぎる場合に生じる主なデメリットを詳しく解説します。
欠品による販売機会損失
在庫月数が低いと、販売の勢いに在庫が追いつかず、欠品が発生しやすくなります。
人気商品や季節商品など、需要が集中するタイミングで在庫切れが起きると、販売機会を逃すだけでなく、競合他社への顧客流出にもつながります。
特にネットショップやECモールでは、欠品状態になると検索順位が下がる、販売ページが非表示になるなど、売上回復までに時間がかかるケースもあります。
欠品は単なる販売損失にとどまらず、長期的な売上・ブランドイメージにも影響を及ぼす点に注意が必要です。
仕入れコストの増加
在庫を少なく保とうとしすぎると、仕入れや補充を小口で頻繁に行う必要が出てきます。
その結果、発注回数の増加によって仕入れ単価の上昇や運送費の増加を招き、トータルコストが高くなってしまいます。
特に製造業では、部品や資材の在庫が不足すると生産ライン全体が止まる可能性があり、納期遅延や追加コスト発生といったリスクが生じます。
顧客満足度の低下
欠品や納期遅延が発生すると、顧客に信頼できない、対応が遅いといった印象を与えてしまいます。
特にBtoB取引では、一度の欠品が取引先の生産スケジュールに影響するため、取引関係の悪化にもつながりかねません。
また、BtoCの場合も、欲しいときに商品が購入できないことが続くと、リピート率が下がり、ブランド離れを引き起こします。
在庫月数を過度に抑えることは、コスト削減にはつながっても、顧客体験の質を下げるリスクがあることを意識する必要があります。
在庫月数とは:在庫月数の求め方を把握する重要性
在庫月数を定期的に算出することは、在庫管理の現場だけでなく経営判断にも大きな意味があります。
在庫月数の求め方を把握する重要性を解説します。
在庫切れを防ぎ安定供給を維持する
在庫月数を把握していれば、どの時期にどの商品の在庫が減るかを予測でき、欠品を未然に防げます。
安定した供給体制は、顧客の信頼にもつながります。
過剰在庫を防止し資金繰りを安定させる
在庫月数をモニタリングすることで、過剰在庫の兆候を早期に発見できます。
過剰在庫を減らすことは、資金繰りの改善に直結します。
仕入れや発注の精度を高める
販売データをもとに在庫月数を分析することで、需要に応じた発注数を決められます。
経験や勘に頼らず、データドリブンな発注が可能になります。
経営判断の指標として活用できる
在庫月数は、在庫回転率や売上成長率とあわせて見ることで、企業全体の経営効率を測る指標になります。
部門別に比較すれば、どの部署で在庫効率が低いかも明確になります。
在庫月数とは:在庫月数の求め方
在庫月数を求めるためには、販売実績や安全在庫を考慮して計算するのが一般的です。
在庫月数の求め方を解説します。
販売実績を基にした算出方法
基本的な計算式は以下の通りです。
「在庫月数 = 現在の在庫数量 ÷ 直近数か月の平均販売数量 」
たとえば、直近3か月の販売実績が月平均100個で、現在の在庫が250個であれば、在庫月数は2.5か月となります。
この数値を定期的に算出し、基準値と比較することで、在庫の過不足を判断できます。
安全在庫を考慮した計算方法
実務では、需要の変動や納期遅延に備えて安全在庫を加味することが重要です。
「在庫月数(安全在庫込み)=(現在の在庫数量 – 安全在庫数量) ÷ 平均販売数量」
安全在庫を引いた上での在庫月数を確認すれば、実質的に「あと何か月分の販売が可能か」をより正確に把握できます。
在庫月数とは:在庫月数を活用した在庫管理改善方法
在庫月数は、単に数値を出すだけでなく、日々の在庫管理改善に活かすことで真価を発揮します。
在庫月数を活用した在庫管理改善方法を解説します。
需要予測と組み合わせた活用
過去の販売データや季節要因をもとに需要予測を行い、在庫月数の基準値を調整することで、より精度の高い在庫管理が可能になります。
在庫回転率との併用
在庫月数は、在庫回転率と密接な関係があります。
両者を併用して分析すれば、商品別・カテゴリー別の在庫効率を多角的に評価できます。
販売データを用いた発注リードタイム調整
発注から納品までのリードタイムを考慮し、在庫月数が基準を下回るタイミングで自動発注できるようにすることで、欠品を防ぎつつ在庫の最適化を実現します。
システム化によるリアルタイム管理
エクセルや手作業での管理では更新のタイムラグが発生しがちですが、クラウド型の在庫管理システムを導入すれば、在庫月数をリアルタイムで可視化できます。
スマートフォンやパソコンから在庫状況を自動更新でき、過去データをもとに在庫月数の変化を分析することも可能です。
在庫月数を理解し在庫管理の最適化にzaico
在庫月数は、現在の在庫量がどれだけの期間販売に対応できるかを把握するための重要な指標です。
在庫月数が高すぎれば資金効率が悪化し、低すぎれば欠品リスクが増加します。
定期的に在庫月数を算出し、販売実績や需要予測と照らし合わせることで、適正在庫を維持できます。
「クラウド在庫管理システムzaico」は、在庫の更新内容をリアルタイムで同期して在庫を可視化し、在庫管理の負担、欠品・過剰在庫を大幅に削減するクラウド在庫管理アプリになり、インターネット環境さえあれば時間や場所を問わずにアクセスできます。
製造業、小売・卸売業、建設・不動産業を中心に、さまざまな企業・団体で導入し、在庫管理にかかる時間を大幅にカットするなど、効果を実感いただいています。
在庫月数や在庫管理の最適化に役立つ在庫管理システムをお探しの方はお気軽にzaicoにお問い合わせください。